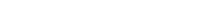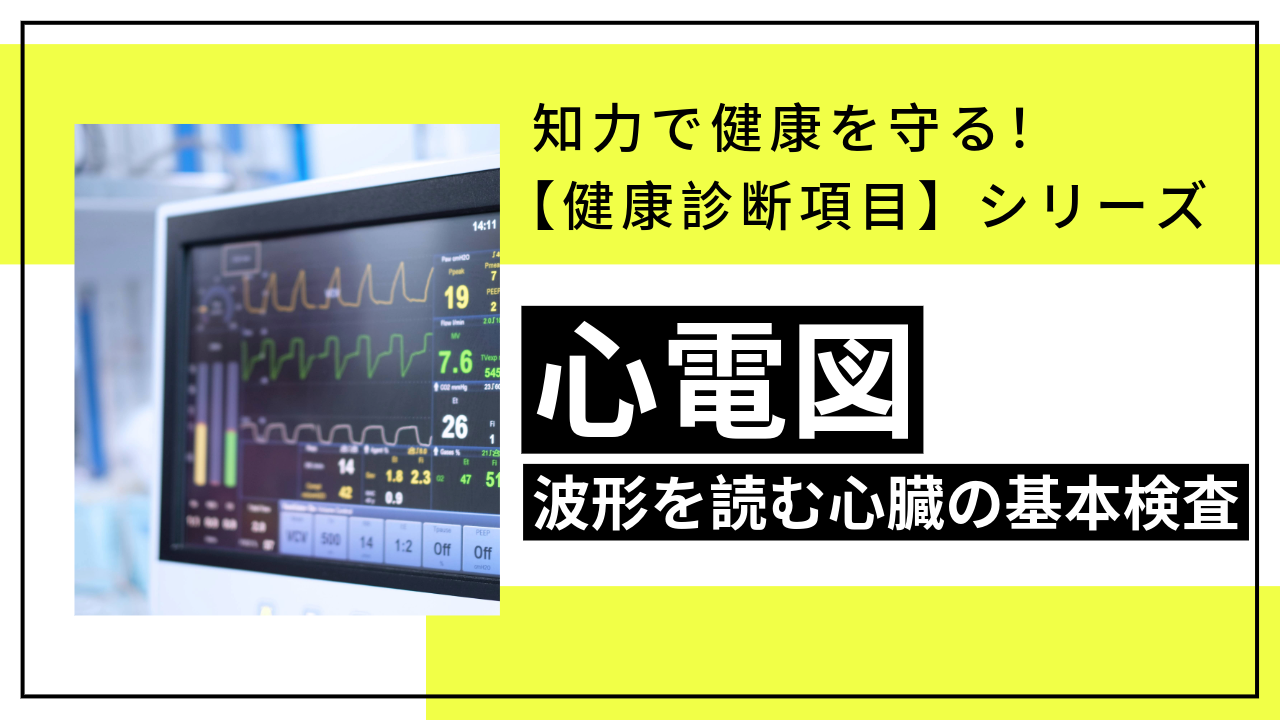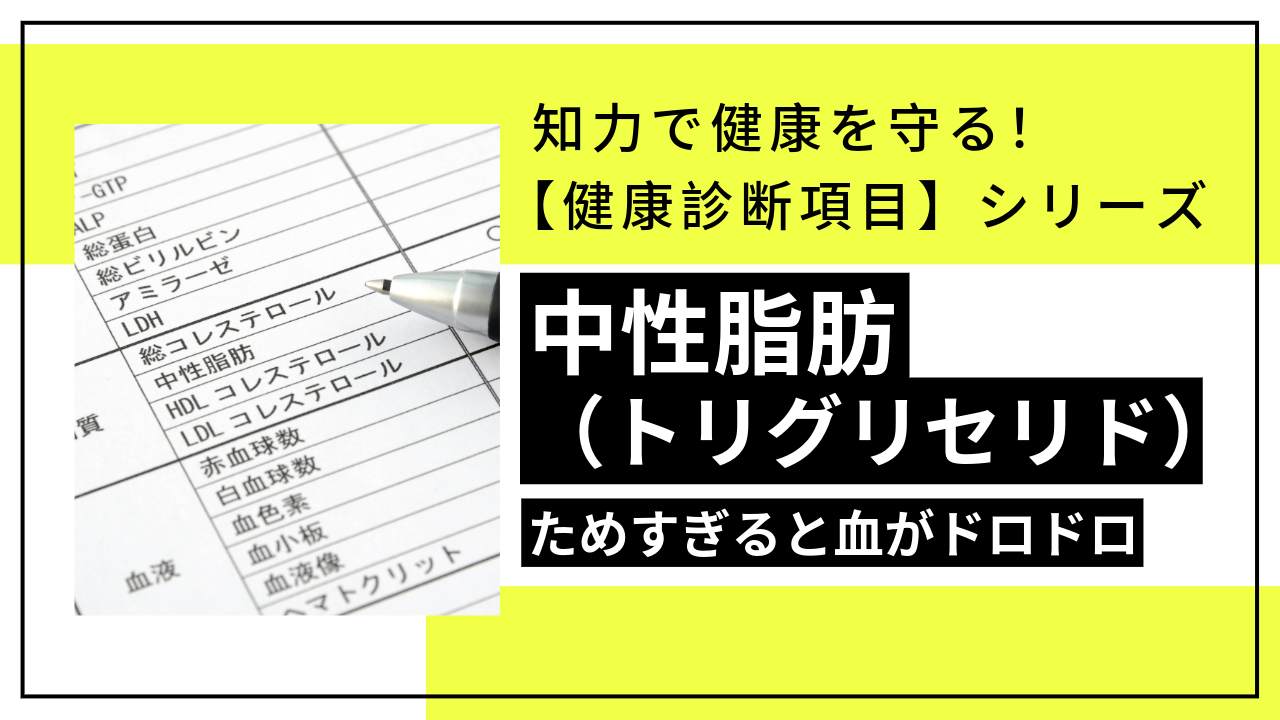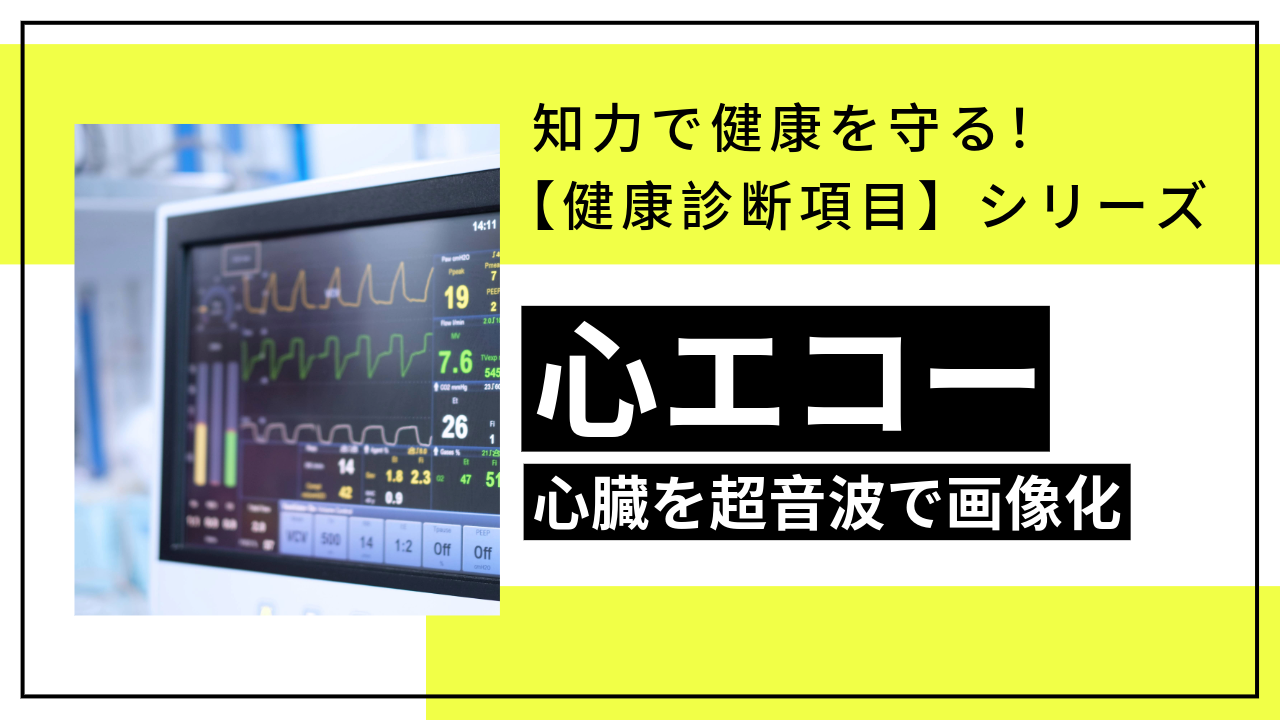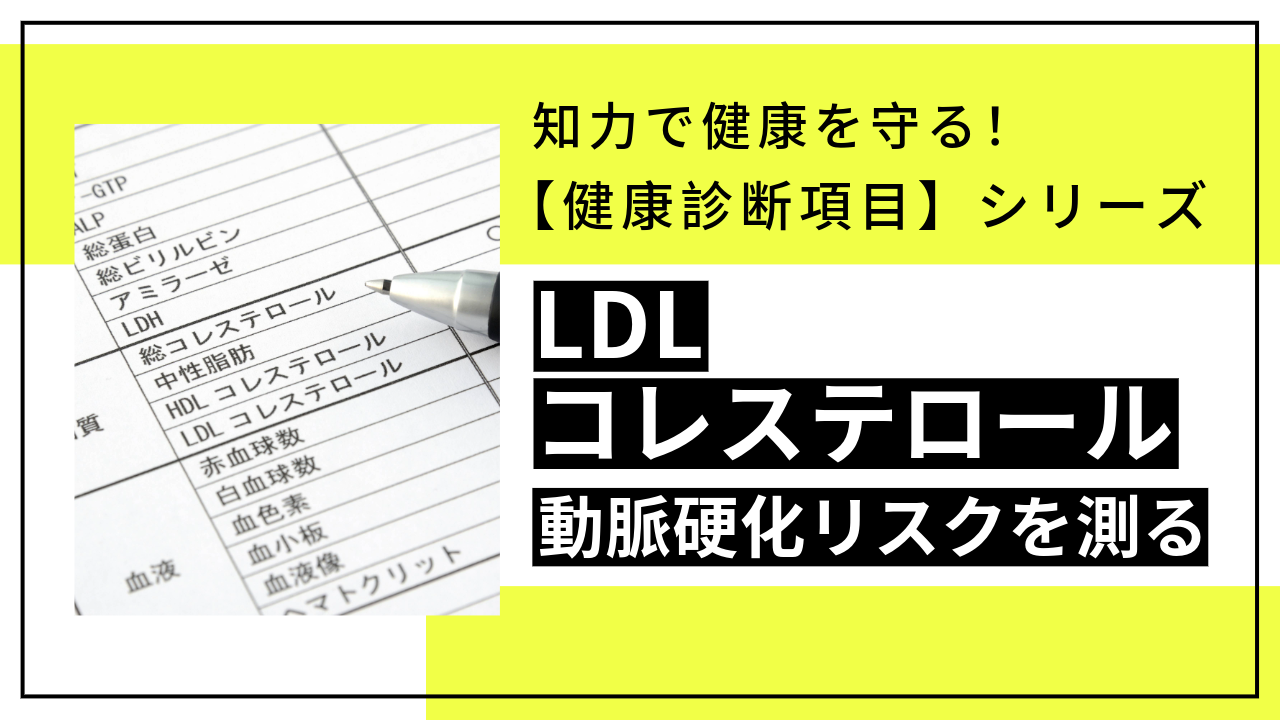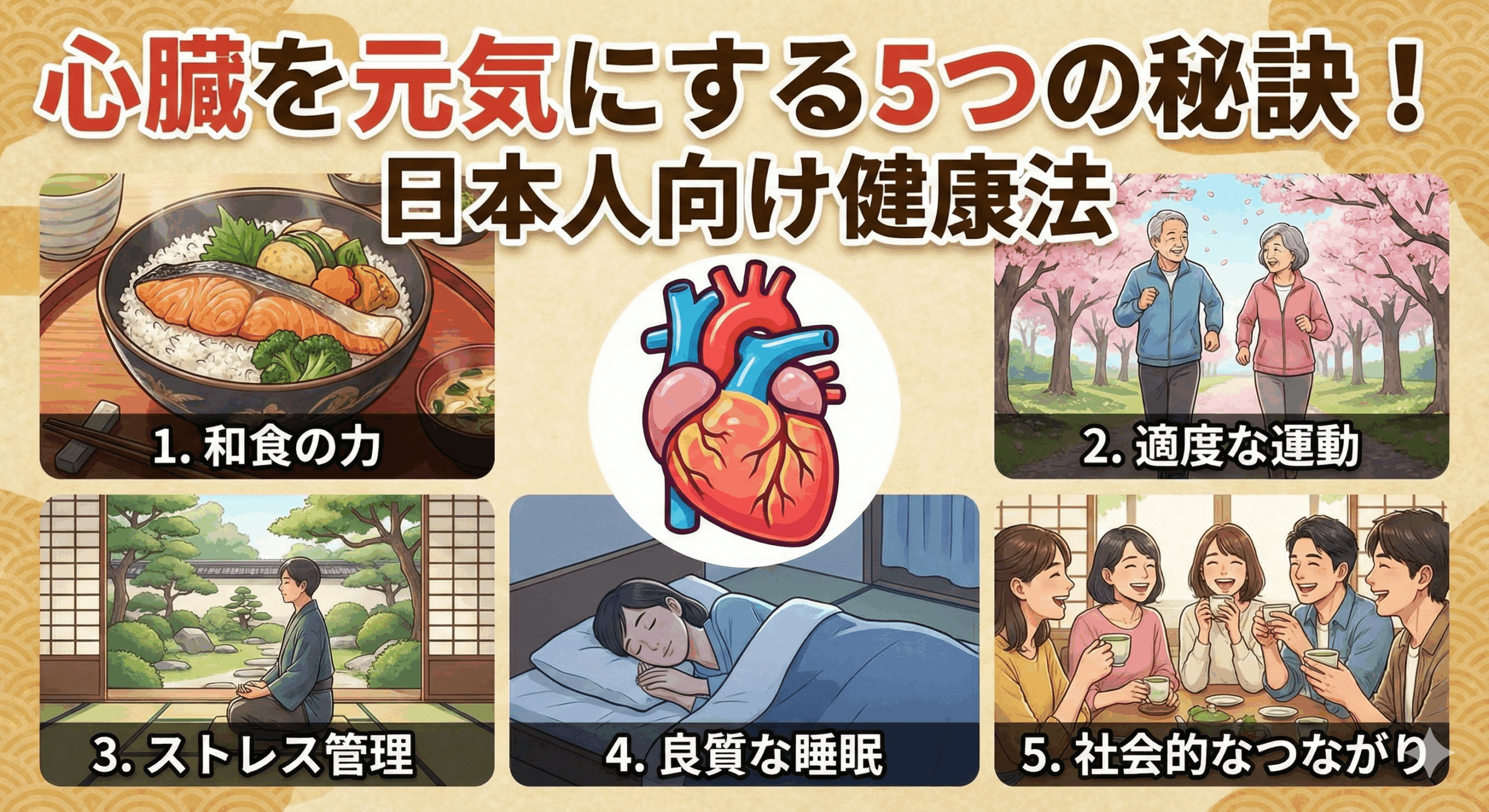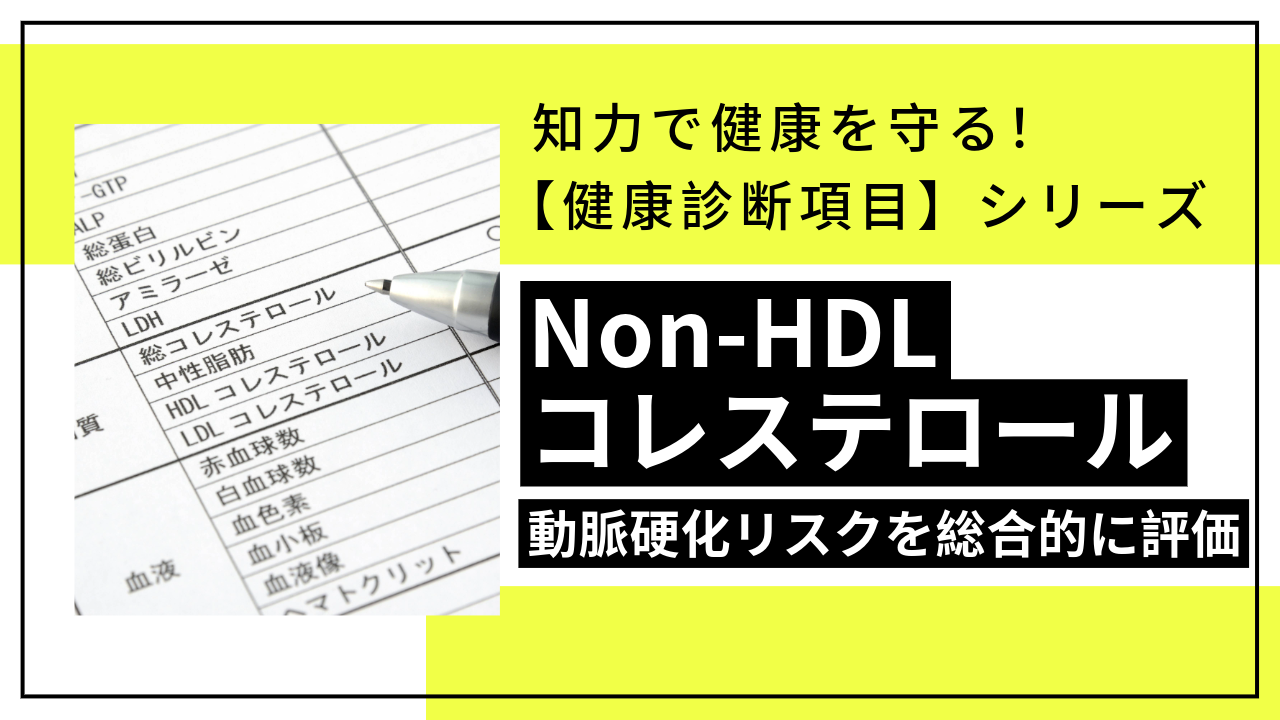【心疾患】要注意健康診断項目とその他の検査方法

心疾患に関連する健康診断の項目
心疾患とは心臓の病気の総称。何らかの原因で心臓に異常が起きて、血の流れがうまくいかなくなる状態のことです。
| 病名 | 詳細 |
| 高血圧 | 血圧が基準値よりも高くなって状態 |
| 動脈硬化(どうみゃくこうか) | 血管の弾力性が失われている状態 |
| 不整脈(ふせいみゃく) | 心臓が不規則に動く病気 |
| 狭心症(きょうしんしょう) | 心臓の血管が詰まるまた狭くなる病気 |
| 弁膜症(べんまくしょう) | 心臓にある4つの弁のいずれかに異常が起きる病気 |
| 心筋梗(しんきんこうそく) | 心臓を動かす筋肉に血液が届かなくなり障害が起きる病気 |
心疾患に関連する健康診断では、主に下記のような心臓や血管の病気のリスクを評価できます。
ここでは、血圧測定や血液検査、尿検査、胸部X線検査、心電図検査などの健康診断で実施される検査について解説します。
1.血圧測定
血圧測定は、心臓や血管の健康状態を簡易に確認できる基本的な検査です。血圧が高い状態が続くと、血管が硬くもろくなり心疾患のリスクが高まります。
血圧は下記の基準値を超えると高血圧と診断されます。
| 収縮期血圧(上の血圧) | 拡張期血圧(下の血圧) | |
| 診察室高血圧 | 140mmHg以上 | 90mmHg以上 |
| 家庭高血圧 | 135mmHg以上 | 85mmHg以上 |
血圧は病院で測定すると緊張などによりやや高くなるため、自宅で測定する家庭血圧のほうが普段の血圧に近く正しい数値とされています。
また、血圧は年齢や生活習慣、ストレスなどさまざまな要因で変動するため、定期的に測定することが大切です。血圧をしっかり管理することが心疾患の予防につながります。
2.血液検査、尿検査
血液検査、尿検査では、心疾患のリスクを評価するために貧血の有無や血の中の脂質、糖の量、たんぱく質の量を調べます。検査項目と正常値は下記の通りです。なお、検査の正常値は医療機関により異なる場合があります。
| 検査 | 項目 | 正常値 |
| 貧血検査 | 血色素量(Hb) | 男性:13.0~16.4.0g/dL 女性:12.0~14.6g/dL |
| 赤血球数 | 男性:4.20~5.50×106/μL 女性:3.80~5.10×106 /μL | |
| 血中脂質検査 (血液中の脂質の量を調べる) | 中性脂肪(トリグリセリド) | 30~149mg/dL |
| Non-HDLコレステロール | 90〜149mg/dL | |
| HDLコレステロール(善玉) | 40〜96mg/dL | |
| LDLコレステロール(悪玉) | 120mg/dL未満 | |
| 血糖検査 (血液中の糖の量を調べる) | 血糖値(FPG) | 80~100mg/dL |
| HbA1c(NGSP) | 4.6~5.6% | |
| 尿検査 | 尿蛋白(尿中のタンパク質の量) | 陰性(-) |
出典:国立循環器病研究センター「主な血液検査の基準値一覧表」
出典:日本人間ドック学会・予防医療学会 「尿検査」
出典:日本人間ドック学会・予防医療学会「血液検査」
ヘモグロビンや赤血球が正常値より低く貧血傾向であると、心臓への負担が強くなり心疾患のリスクが高まります。
血の中の脂質や糖の量が正常値を超えている状態であると、血の流れが悪くなったり、血管がもろくなったりするため、心筋梗塞や狭心症のリスクが高まります。
血液検査は心疾患の発見において重要です。異常値が見られた場合は生活習慣の見直しや治療を検討することが大切です。
血色素量についてもっと詳しく→
中性脂肪(トリグリセリド)についてもっと詳しく→
Non-HDLコレステロールについてもっと詳しく→
HDLコレステロールについてもっと詳しく→
LDLコレステロールについてもっと詳しく→
血糖値(FPG)についてもっと詳しく→
HbA1cについてもっと詳しく→
尿蛋白についてもっと詳しく→
3.胸部X線検査
胸部X線検査は、心臓や肺の形、大きさを画像で確認する検査です。下記のように心臓や肺に異常があるかどうかを確認できます。
| 心臓 | 正常な場合、心臓の形や大きさに異常は見られない。心肥大(しんひだい)や心不全(しんふぜん)が疑われる場合、心臓が大きく写る。 |
| 肺 | 心臓と肺は密接に関係している。心不全の患者さんでは、肺水腫(はいすいしゅ:肺に水がたまった状態)が現れることが多く、X線検査は早期発見に役立つ |
胸部X線検査は、心臓と肺の健康状態を幅広く評価するために大切な検査です。
4.心電図検査
心電図検査は、心臓の動きを波形により記録する検査。心臓のリズムや血流に問題があるかどうか調べることが可能です。
健康な心臓は規則的な波形が見られます。正常な波形ではない場合、心臓のリズムや血流に問題がある可能性があり、心疾患の疑いがあります。
例えば、心筋梗塞の初期段階では波形に特徴的な異常が現れるため、迅速な診断と治療につなげることが可能です。
心電図検査は、症状がない場合でも異常を発見できることもあるため、定期的に受けることを推奨します。心電図検査の詳細を知りたい方はこちらから確認してください。
5.BMI(肥満度指数)
BMI(体重[kg] ÷ 身長[m]²)は、肥満度を示す指標です。肥満は心疾患のリスクを高めます。BMIが適正範囲に収まるよう、バランスの取れた食事や適度な運動を心がけましょう。
| 正常値 | 異常値(肥満の目安) |
|---|---|
| 18.5〜24.9 | 25以上 |
参照元:厚生労働省e-ヘルスネット
心疾患の法定健診以外の検査
法定健診とは、労働安全衛生法で義務付けられている健康診断のことです。法定健診以外の心疾患に関連する検査は下記の通りです。
- 心エコー検査
- 心磁図(しんじず)検査
- 心臓MRI・MRA検査
- 胸部CT検査
- ホルター心電図検査
それぞれの検査の詳細を解説します。
1.心エコー検査
心エコー検査は、超音波で心臓の形や動きを確認する検査です。心疾患の早期発見や治療効果の確認などに役立ちます。
具体的には下記の詳細を確認します。
| 心臓の大きさ | 心臓が大きくなっていないか確認する。心臓が大きくなっている場合は、心肥大や心不全が疑わられる |
| 弁の動き | 心臓にある4つの弁の動きを確認する。弁のいずれかに異常が見られた場合は弁膜症が疑われる |
| 血液の流れ | 心臓の血液の流れに異常がないかを確認する。逆流などが見られる場合は、心臓の弁に異常が起きている弁膜症が疑われる |
異常を確認した場合、その他に必要な検査や治療の計画が立てられる場合があります。心エコー検査の詳細を知りたい方はこちらも参考にしてください。
2.心磁図検査
心磁図検査は、心臓から発生する微弱な磁気をとらえて、心臓の電気活動を画像として確認する検査です。この検査では下記のようなことを確認できます。
- 不整脈がどれくらい重いのか、どこで起きているのかを特定できる
- 心臓が障害されている場所を特定できるため心疾患を早期発見できる
上記のように心疾患の早期発見や重症度の特定に役立つ検査です。
3.心臓MRI・MRA検査
心臓MRI検査は、磁気を使って心臓や周囲の組織を画像として表示する検査。心臓の動きや形、大きさなどを広範囲に調べられます。MRA検査は、冠動脈(かんどうみゃく:心臓の重要な血管)などの血管の様子を画像化して調べる検査です。
これらの検査では、現状の状態だけでなく、血管にたまっている脂質の塊などを調べることができ、将来の心疾患のリスクを評価できます。また、MRI・MRA検査は放射線を使わずに、心臓を詳細に調べることができる安全性の高い検査です。
4.胸部CT検査
胸部CT検査は、X線により胸部全体を調べる検査です。心臓だけでなく、周囲にある重要な血管、気管を鮮明に調べることができます。他にも造影剤の使用や特殊な撮影技術により、心臓の動きも鮮明に撮影可能です。
CT検査でも、血管にたまっている脂質の塊などを調べることができ、狭心症や心筋梗塞を発症するリスクを評価できます。
5.ホルター心電図検査
ホルター心電図検査は、24時間にわたり心電図を記録する検査です。日常生活における波形の変化を確認できるため下記のことがわかります。
- 不整脈の種類や発生頻度、持続時間
- めまいや胸の痛み、動悸(どうき:胸がドキドキする症状)などの症状が起きている際の波形
ホルター心電図は、夜間に起こる不整脈や一時的な心臓の動きの乱れを把握しやすく、発作性の症状がある場合の診断に役立ちます。
心疾患の法定健診以外の検査を受ける方法
心疾患の法定健診以外の検査を受けるには、医療機関で医師の診察を受け、必要に応じた紹介や指示を受けることが一般的です。
または、特定の医療機関で人間ドックを申し込む方法もあります。検査内容によって費用が異なり、場合によっては高額になる可能性もあるため注意が必要です。
健康診断などにより心疾患リスクが高いと判断された場合、定期的に精密検査を受けることで、心臓の健康状態をより詳細に把握できます。気になる方は、かかりつけの医師に相談してみてもよいでしょう。