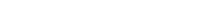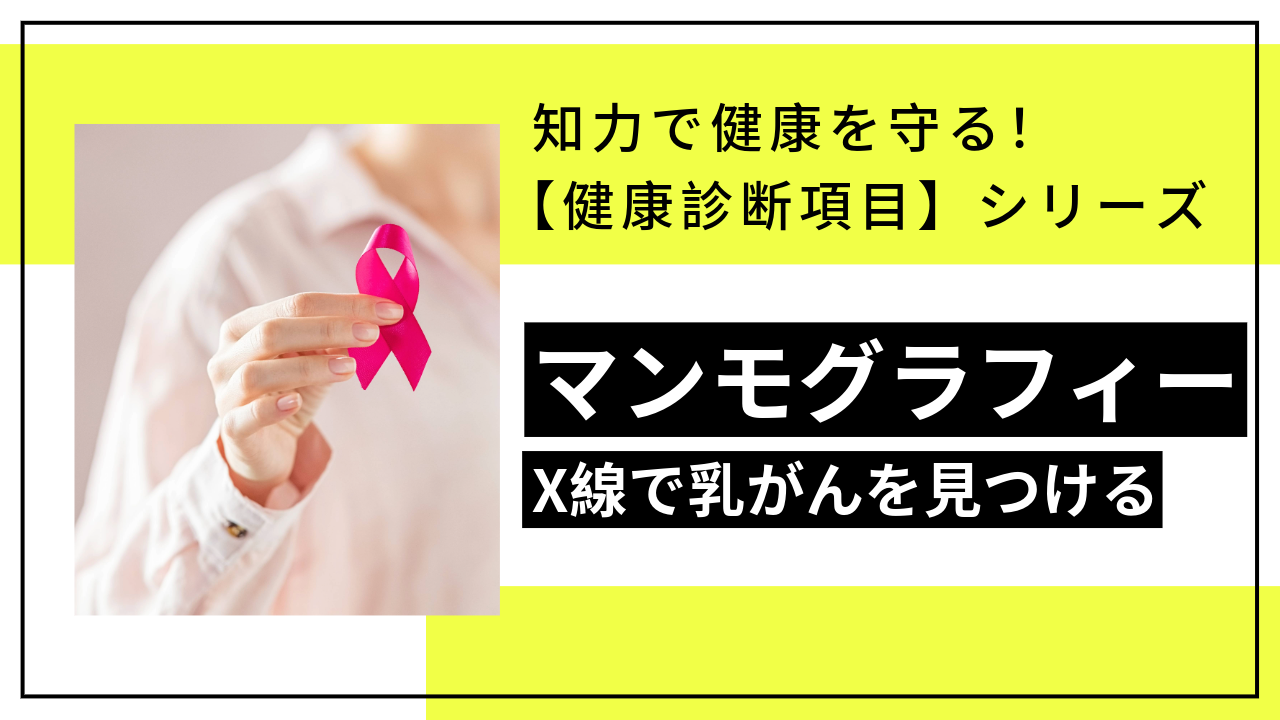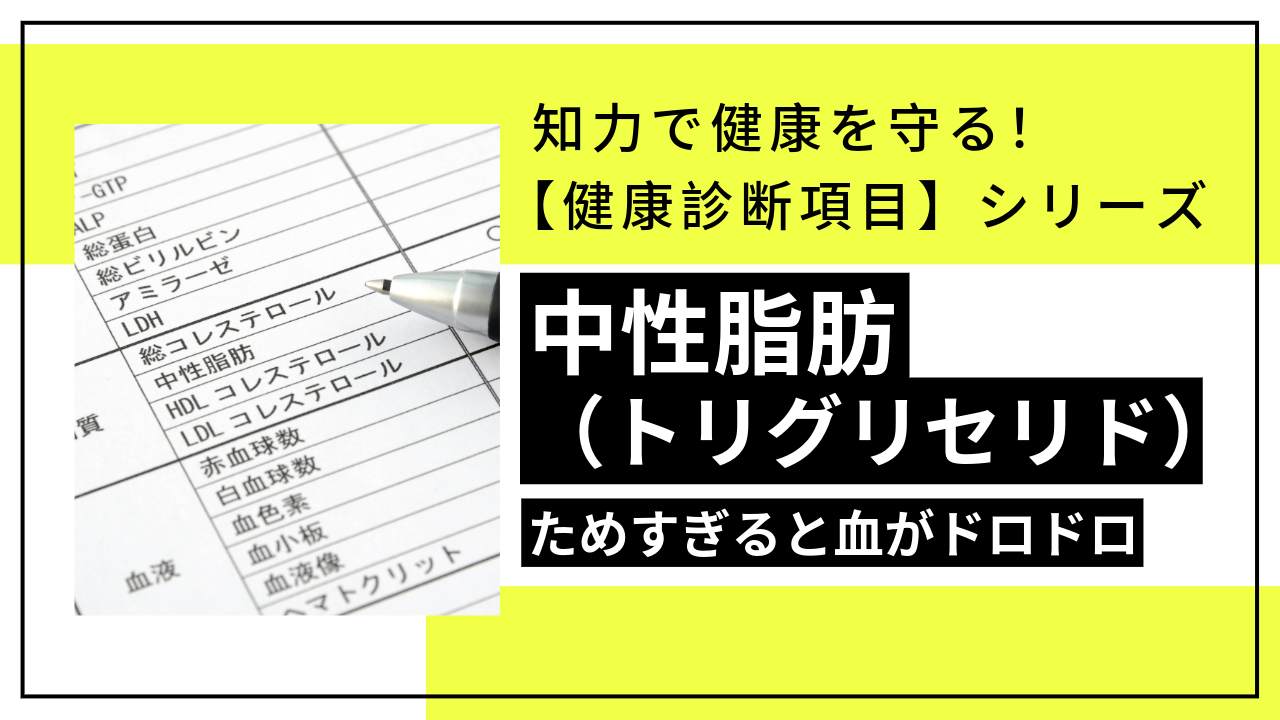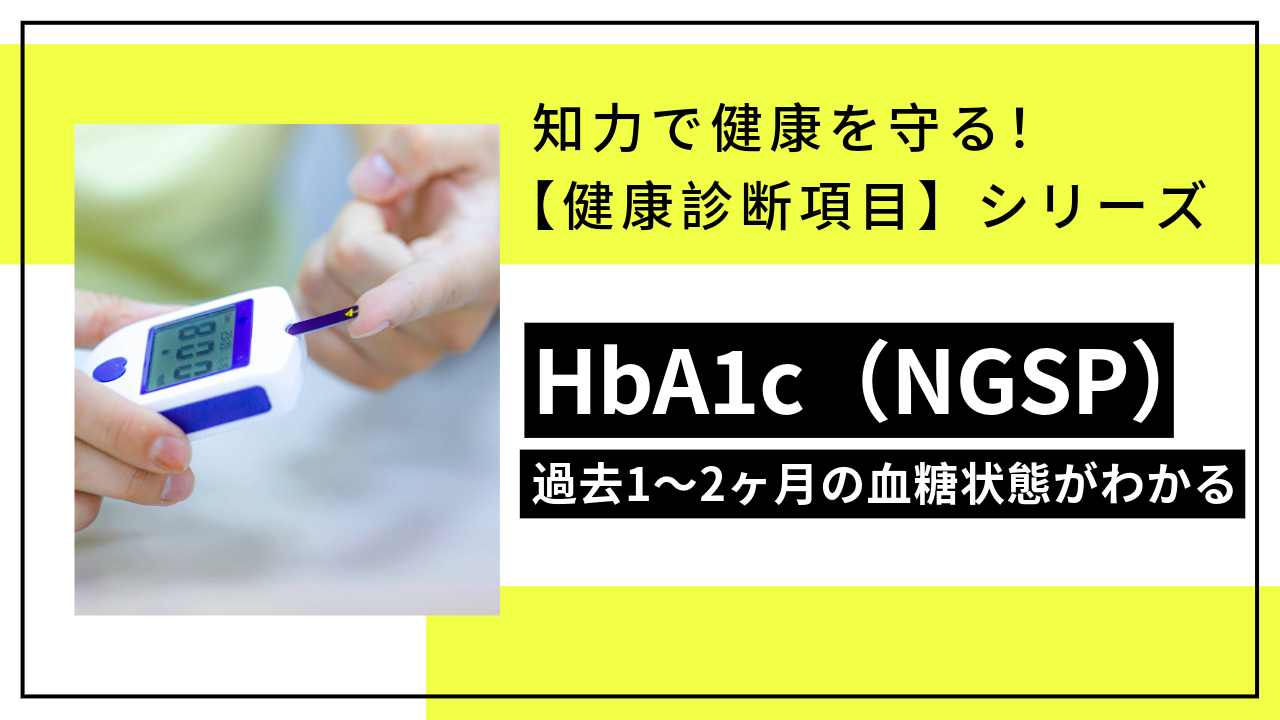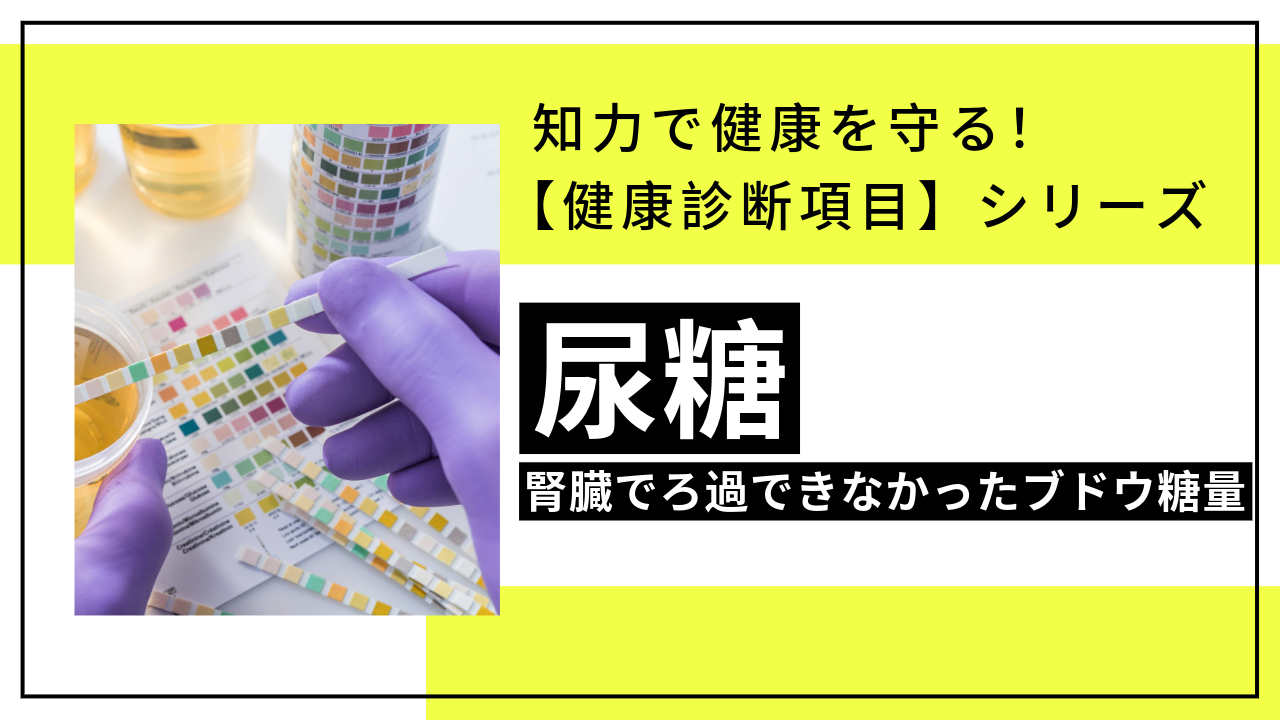【健康診断項目】心臓を超音波で画像化「心エコー」
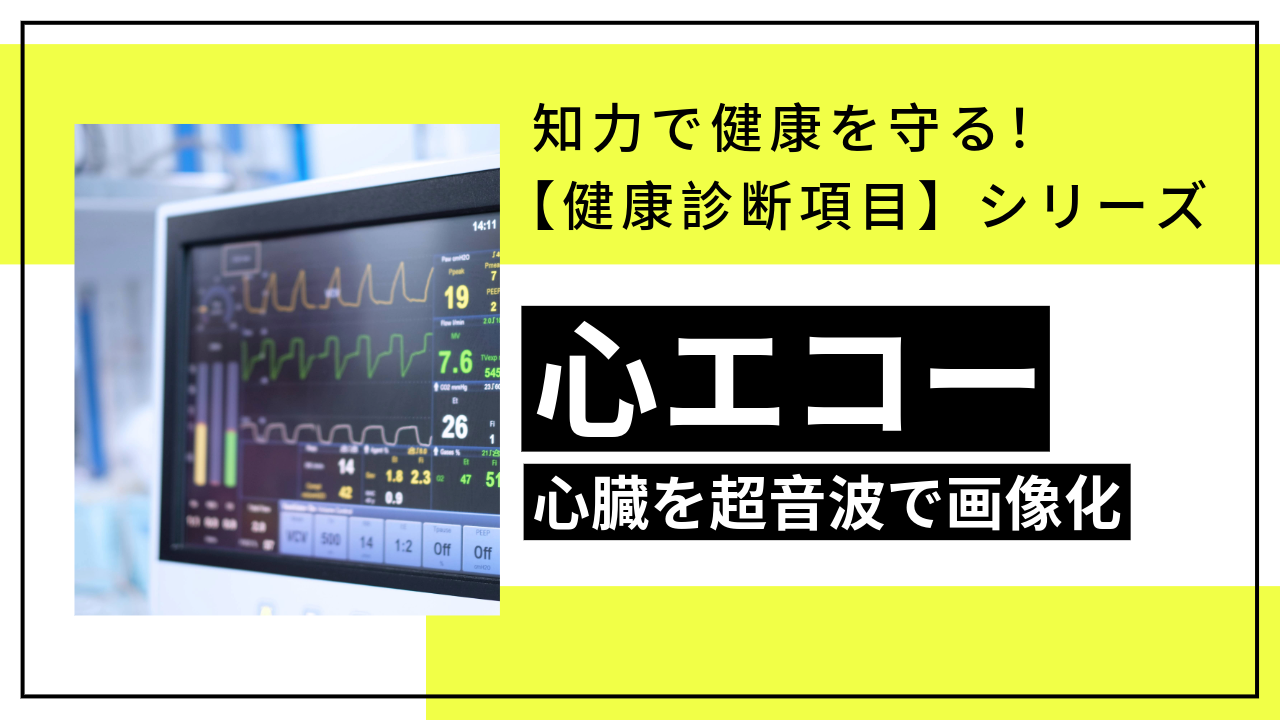
心エコー検査とは?
心エコー検査とは、超音波を利用して心臓の状態を画像化する検査です。心エコー検査では、主に下記のことを確認します。
| 心臓の形や働き | 心臓が大きくなっていないか、正常に動いているか |
| 心臓の弁の動き | 心臓にある4つの弁の開閉に異常はないか |
| 心臓内の血流の流れ | 血液が正常に流れているか、逆流していないか |
検査の流れは超音波の通過をよくするために、胸にゼリーをつけて探触子(たんしょくし:超音波を発生または受診する医療機器)を肌に押し当てて実施します。
探触子を押し当てたときに少し痛みを感じることもありますが、心臓の異常を安全かつ早期に発見できる検査です。
心エコー検査の正常値
心エコー検査で数値化されている項目を一部紹介すると下記の通りです。
| 検査項目 | 詳細 | 男性の正常値 | 女性の正常値 |
| 左室拡張末期容積係数 | 左心室(さしんしつ:全身に血圧を送り出す部屋)が最も広がったときの空間の大きさを表した数値 | 79mL/m2 | 71mL/m2 |
| 左室収縮末期容積係数 | 左心室が最も縮んだときの空間の大きさを表した数値 | 32mL/m2 | 28mL/m2 |
| 左室心筋重量係(LVMI) | 左心室の筋肉の重さを表した数値 | 64±12g/m2 | 56±11g/m2 |
| 左房容積係数(LAVI) | 左心房(さしんぼう:肺から送られてきた血液を受け取る部屋)の空間の大きさを表した数値 | 23±6mL/m2 | 24±6mL/m2 |
| 左室駆出率(LVEF) | 左心室の血液を送り出す力を表した指標 | 64±5% | 66±5% |
| 右室拡張末期容積係数 | 右心室(うしんしつ:肺へ血液を送り出す心室)が最も広がったときの空間の大きさを表した数値 | 87mL/m2 | 74mL/m2 |
| 右室収縮末期容積係数 | 右心室が最も縮んだときの空間の大きさを表した数値 | 44mL/m2 | 36mL/m2 |
心エコー検査では、上記のような項目を調べながら、心臓の形や働きを評価して、異常がないかを判断します。
異常値からわかること
心エコーの検査項目に異常が見られた際は、何らかの心疾患を発症している可能性があります。例えば下記のような病気です。
| 病名 | 詳細 |
| 心臓弁膜症(しんぞうべんまくしょう) | 心臓にある4つの弁のいずれかが正常に動かなくなる病気。血液の逆流などが起きる。 |
| 心筋炎(しんきんえん) | 心臓の筋肉に炎症が起きる病気。炎症した部位の動きがおかしくなったり心臓が大きくなったりする。 |
| 肥大型心筋症(ひだいがたしんきんしょう) | 心臓が大きくなり血液を送り出す力が弱くなる病気。 |
| 拡張型心筋症 | 心臓の縮む力が弱くなる病気。 |
| 二次性心筋症(にじせいしんきんしょう) | 特定の原因や全身の病気との関係が明らかな心筋症。遺伝や自己免疫(免疫が自分の体を攻撃してしまう)などが関係している |
| たこつぼ症候群 | 心臓が一時的に異常な縮み方をして、突然の胸の痛みや息苦しさを引き起こす症候群 |
| 高血圧性心疾患 | 高血圧が原因で心臓が大きくなり、血液を送り出す力が弱くなる病気 |
| 心膜疾患(しんまくしっかん) | 何らかの原因で心臓を包む膜に炎症が起きる病気。膜の中に液体がたまることがある |
| 虚血性心疾患(きょけつせいしんしっかん) | 動脈硬化(どうみゃくこうか:血管の弾力性が失われている状態)や血栓(けっせん:血の塊)により心臓の血管が狭くなり、栄養や酸素が十分に行き届かない病気。心臓の動きに異常が見られる |
| 感染性心内膜炎(かんせんせいないまくえん) | 心臓の壁や弁に細菌が付着して発症する感染症。血の流れにのった細菌が心臓に到達することで発症する |
心エコー検査で異常があった場合は、医師に相談して必要な治療を受けることが大切です。
異常値の原因は?
心臓エコー検査で異常が見られる原因として、前述したような心臓の病気だけでなく、高血圧や脂質異常症(血液中に脂質が多い状態)、糖尿病(血液中に糖が多い状態)などの生活習慣病の影響が考えられます。
特に生活習慣病はさまざまな心疾患の原因になる動脈硬化を進行させてしまいます。これらの病気を引き起こさないためにも、下記のような生活習慣の乱れには注意が必要です。
- 塩分のとりすぎ
- アルコールのとりすぎ
- 喫煙
- 運動不足
- 睡眠不足
- 強いストレス
また、心筋炎と弁膜症といった病気は、感染症や加齢なども発症の原因になります。心疾患を早期発見または発症予防するためにも、定期的に健康診断を受けることや規則正しい生活を心がけましょう。
異常値を治すために
心エコー検査で見られた異常値を治すためには、原因となっている病気の治療や生活習慣の改善が必要です。
具体的な治療方法は、薬物療法や外科手術など多岐にわたります。例えば、心臓弁膜症が重い方は、人工の弁に置き換える外科手術が行われることもあります。
生活習慣の改善においても定期的な医師の診察や検査が大切です。医師の指導のもとに食事療法や運動療法を実施していかなければ、効果的な治療につながらないためです。心エコー検査で異常が見られたら、医師と相談しながら原因を解決していきましょう。