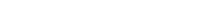【認知症】要注意健康診断項目とその他の検査法
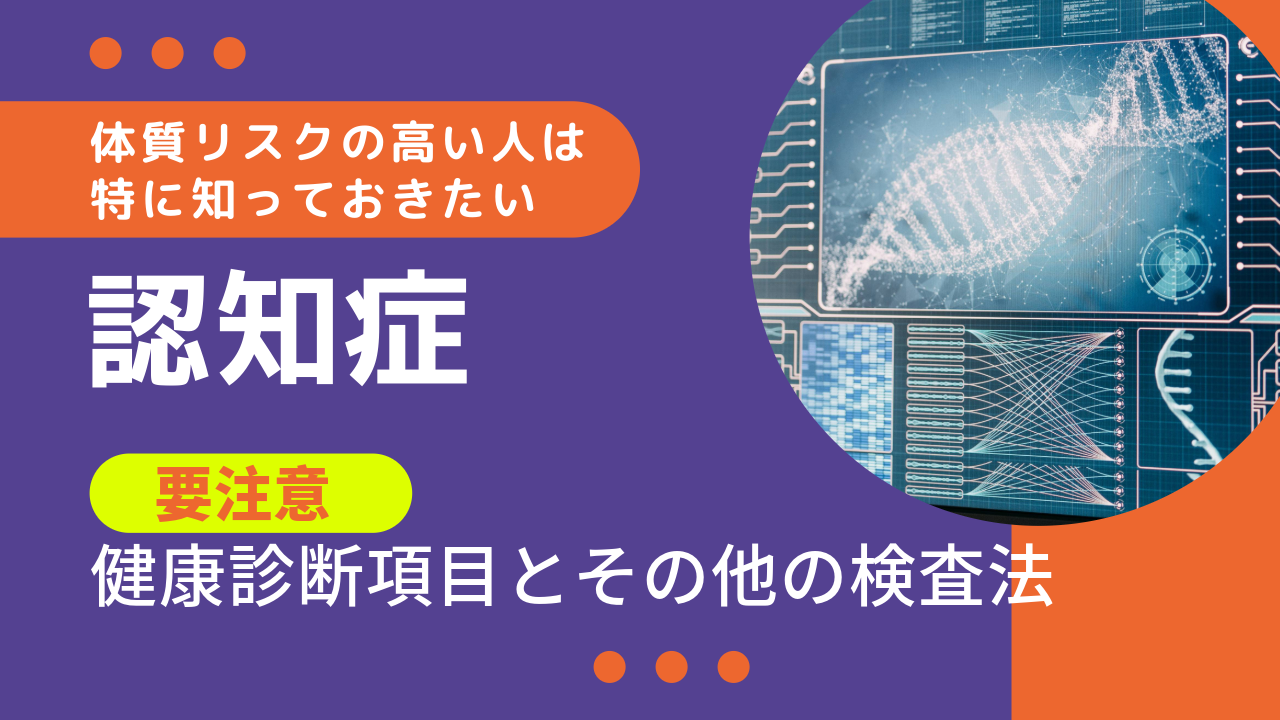
認知症は高齢者だけの病気と思われがちですが、中年期からの生活習慣や健康状態が将来のリスクに大きく関係していることがわかっています。
特に働き盛りの会社員にとって、認知症は決して無関係な話ではありません。長時間労働、食生活の乱れ、運動不足、ストレスなど、日々の習慣が知らず知らずのうちに認知症のリスクを高めている可能性があります。
認知症に関連する健康診断項目
認知症は生活習慣病や血管の健康状態と深い関わりがあり、健康診断で確認する項目がリスク発見に役立ちます。ここでは、健康診断で確認すべき認知症に関連する主な項目を紹介します。
血圧測定
血圧は脳の健康を左右する重要な指標です。高血圧が続くと脳の血管に負担がかかり、以下の認知症リスクを高める可能性があります。1
血管性認知症
血管の詰まりや破れによる認知機能の低下
アルツハイマー型認知症
高血圧による血管ダメージが間接的に影響
特に働き盛り世代では、ストレスや睡眠不足が血圧を上昇させる要因となるため、健康診断で定期的にチェックすることが大切です。
血糖値
血糖値は、血液中のブドウ糖濃度を示す指標です。糖尿病はアルツハイマー型認知症の発症リスクを約2倍にすることが報告されています。健康診断で血糖値を測定することで、糖尿病の早期発見や血糖値コントロールによる認知症予防できるメリットがあります。2
糖尿病が疑われる場合は、さらに詳細な検査や治療を受けましょう。
脂質検査(LDL・HDLコレステロール、中性脂肪)
脂質検査は、血液中の脂肪分を測定する検査です。LDLコレステロールと中性脂肪(トリグリセリド)値が高いと動脈硬化を引き起こし脳への血流を低下させます。また、HDLコレステロールが低いと、血管の修復機能が低下し血管の健康が損なわれます。3
定期的な脂質検査を受け、必要に応じて食事や運動の改善を行いましょう。
BMI(肥満度指数)
BMI(体重[kg] ÷ 身長[m]²)は、肥満度を示す指標です。肥満は、高血圧や糖尿病を引き起こし認知症リスクを間接的に高めます。また、過度な痩せは、脳の栄養不足を招き認知機能を低下させます。4
BMIが適正範囲に収まるよう、バランスの取れた食事や適度な運動を心がけましょう。
各健康診断項目の正常値と異常値
健康診断で得られる数値は、認知症リスクを把握するうえで重要な手がかりです。認知症リスクと関係の深い検査項目の「正常値」と「異常値」を解説します。健康診断結果の見方を理解し、早期の予防対策に役立てましょう。
血圧
血圧は、心臓から送り出された血液が血管に与える圧力を示します。高血圧は脳の血管に負担をかけ、認知症の原因となる血管性障害を引き起こすリスクが高まります。
| 項目 | 正常値 | 異常値(高血圧) |
|---|---|---|
| 収縮期血圧(mmHg) | 120未満 | 140以上 |
| 拡張期血圧(mmHg) | 80未満 | 90以上 |
参照元:厚生労働省e-ヘルスネット
特に収縮期血圧(上の値)が高い場合は、脳血管へのダメージが大きくなるため注意が必要です。
血糖値
血糖値は、血液中のブドウ糖濃度を示す指標で、糖尿病の早期発見に役立ちます。糖尿病は認知症リスクを高めるため、定期的なチェックが欠かせません。
| 分類 | 正常値 | 異常値(糖尿病疑い) |
|---|---|---|
| 空腹時血糖値 | 70-99 mg/dL | 126 mg/dL以上 |
| HbA1c | 4.6〜6.0% | 6.5%以上 |
参照元:厚生労働省e-ヘルスネット
血糖値やHbA1cが高い場合、糖尿病または予備軍の可能性があります。特定健診では、空腹時採血が原則です。
血糖値についてもっと詳しく→
HbA1cについてもっと詳しく→
脂質(コレステロール、中性脂肪)
脂質異常は動脈硬化を進行させ、脳の血流を悪化させます。これにより血管性認知症のリスクが高まります。
| 項目 | 正常値 | 異常値(要注意) |
|---|---|---|
| LDLコレステロール(悪玉) | 120 mg/dL未満 | 140 mg/dL以上(リスク増加) |
| HDLコレステロール(善玉) | 40 mg/dL以上 | 40 mg/dL未満(保護効果低下) |
| トリグリセリド(中性脂肪) | 150 mg/dL未満 | 空腹時150 mg/dL以上 |
| Non-HDLコレステロール | 150 mg/dL未満 | 170 mg/dL以上(心疾患リスク増加) |
参照元:厚生労働省e-ヘルスネット
脂質検査では、LDLや中性脂肪が高くHDLが低い場合、生活習慣の見直しが求められます。
空腹時中性脂肪または随時中性脂肪が 400mg/dl 以上、もしくは食後採血の場合は、LDL コレステロールに代えて Non-HDL コレステロール(総コレステロールから HDL コレステロールを除いたもの)で評価が可能です。
LDLコレステロールについてもっと詳しく→
HDLコレステロールについてもっと詳しく→
トリグリセリドについてもっと詳しく→
Non-HDLコレステロールについてもっと詳しく→
BMI(肥満度指数)
BMI(体重[kg] ÷ 身長[m]²)は、肥満や痩せすぎを判断する指標です。体格を表す指標として国際的に用いられています。適切な体重を維持することは、血管や脳の健康を守るために重要です。
| 正常値 | 異常値(肥満の目安) |
|---|---|
| 18.5〜24.9 | 25以上 |
参照元:厚生労働省e-ヘルスネット
肥満は高血圧や糖尿病を引き起こし、間接的に認知症リスクを高めます。一方、過度な痩せも脳の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
日本人は欧米人よりもBMIが平均的に低いことが特徴であり、日本肥満学会の基準では25以上を肥満と定義しています。
その他の検査
認知症リスクをより詳しく調べるには、健康診断ではカバーしきれない追加検査が必要になります。認知症リスク評価に役立つ代表的な追加検査は以下のとおりです。
- 頭部MRI検査
- 脳血流シンチグラフィ
- 認知機能検査
- 遺伝子検査
この検査でわかること
頭部MRI検査
頭部MRI(磁気共鳴画像検査)は、脳の構造を詳細に画像化する検査です。特に脳の萎縮や血流障害など、認知症の初期兆候を発見するのに役立ちます。見た目ではわからない脳の異常を可視化できるため、認知症リスクの評価に非常に有用です。
【調べられること】
- アルツハイマー型認知症などに特徴的な症状
- 血管性認知症のリスク因子
- 脳腫瘍や脳の奇形など、その他の疾患の可能性
脳血流シンチグラフィー
脳血流シンチグラフィーは、放射性物質を用いて脳の血流状態を調べる検査です。MRIが構造を確認するのに対し、この検査では血流から脳の機能面を評価します。
【調べられること】
- アルツハイマー型認知症や血管性認知症の初期兆候を検出
- 認知機能低下が起きている可能性を示唆
脳血流の状態を把握することで、早期治療や予防策を講じるための重要な手掛かりとなります。
認知機能検査
認知機能検査は、脳の働きを直接評価する簡易検査です。短時間で実施でき、体への負担が少ないのが特徴です。自覚症状がなくても認知機能の低下が見つかる場合があり、早期の介入が可能になります。
代表的な認知機能検査は以下のとおりです。
| 検査項目 | 概要 |
|---|---|
| MMSE (Mini-Mental State Examination) | 言語・記憶・図形認識・計算力などを評価する検査で軽度認知障害(MCI)のスクリーニングに役立つ |
| MoCA (Montreal Cognitive Assessment) | MMSEよりも詳細な認知機能を評価でき、糖尿病患者の認知機能障害の発見にも有効 |
【調べられること】
- 記憶力や注意力の低下
- 空間認識や判断力の問題
認知機能検査は簡便かつ効果的であり、初期段階での認知症予防につながります。
遺伝子検査
認知症には遺伝的要因が関係する場合があります。特にアルツハイマー型認知症では、特定の遺伝子(APOE ε4など)がリスクを高めることが知られています。
医療機関での遺伝子検査は、遺伝的な認知症リスクの有無や、APOE ε4など特定の遺伝子変異の有無を調べることが多いです。しかし、APOE ε4など特定の遺伝子に変異が有ると必ず認知症を発症するというわけではなく、また、変異が無い人でも認知症を発症する可能性があります。
一方、Zene360の解析では、総合的なリスク評価のため、APOE ε4など影響の強い特定の遺伝子変異は除外し、ポリジェニックリスクスコア(PRS)を用いて複数の遺伝的要因を解析しています。これは、なりやすさを「有無」ではなく「傾向値」として提供することが大きな違いとなります。
どちらの遺伝子検査も認知症になる可能性を示すものであり、診断そのものではありません。
検査結果に基づき、生活習慣の見直しや専門医のフォローを受けることが重要です。
この検査はどこで受ける?
認知症リスクを詳しく知るための追加検査は、通常の健康診断には含まれていません。そのため、自分で希望して受ける必要があります。以下に、追加検査を受診するための具体的な流れと手順を説明します。
かかりつけ医に相談する
健康診断の結果や日常の気になる症状について、まずはかかりつけ医に相談しましょう。医師が状況に応じ、専門医への紹介状を作成してくれたり、必要に応じた追加検査を提案してもらえたりします。
【相談時のポイント】
- 健診結果で「要精密検査」となった項目があれば、その意味や必要な対応を尋ねる
- 「物忘れが増えた」「集中力が続かない」などの具体的な症状を伝える
- 認知症の家族歴がある場合、その情報も共有する
脳神経内科や認知症外来を受診する
認知症リスクを調べるためには、脳神経内科や認知症外来を受診するのが効果的です。健康診断結果を持参して、地域の脳神経内科や専門クリニックを訪問してください。インターネットで「認知症外来+地域名」を検索すると、近隣の医療機関を見つけることができます。
受診した場合は、以下のような追加検査や診断を行います。
【受診のメリット】
- 頭部MRIや脳血流シンチグラフィーなどの高度な検査が受けられる
- 認知機能検査(MMSEやMoCA-Jなど)で記憶力や判断力を詳しく評価
- 専門的なアドバイスやリスクに応じた治療プランを提案してもらえる
健診施設のオプション検査を活用する
近年では、健康診断のオプションメニューとして認知症関連の検査を提供する施設が増えています。会社の健康診断でもオプションを選択できることもあるため、チェックしておくとよいでしょう。
【注意点】
- 検査費用は自己負担になる場合が多いため事前に費用を確認
- 事前予約が必要な場合があるため申し込み方法をチェック
脳ドックを検討する
脳ドックは、脳や血管の状態を詳しく調べるための総合的な検査プランです。頭部MRIやMRA(血管の画像検査)などがセットになっており、認知症リスクの把握に役立ちます。
費用は施設によって異なりますが一般的には数万円程度です。健診施設や病院のプランを比較し、自分のニーズに合った内容を選びましょう。
【脳ドックのメリット】
- 脳や血管の状態を総合的に評価可能
- 認知症だけでなく、脳梗塞や脳出血などの他の疾患リスクも発見可能
- 健診施設や専門病院で手軽に受診可能
参考文献
・日本老年医学会「認知機能の評価法と認知症の診断」
・認知症診療ガイドライン2017第4章
・認知症診療ガイドライン2017第14章
・日本人間ドック学会「検査表の見方」
・日本老年医学会「認知機能の評価法と認知症の診断」