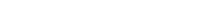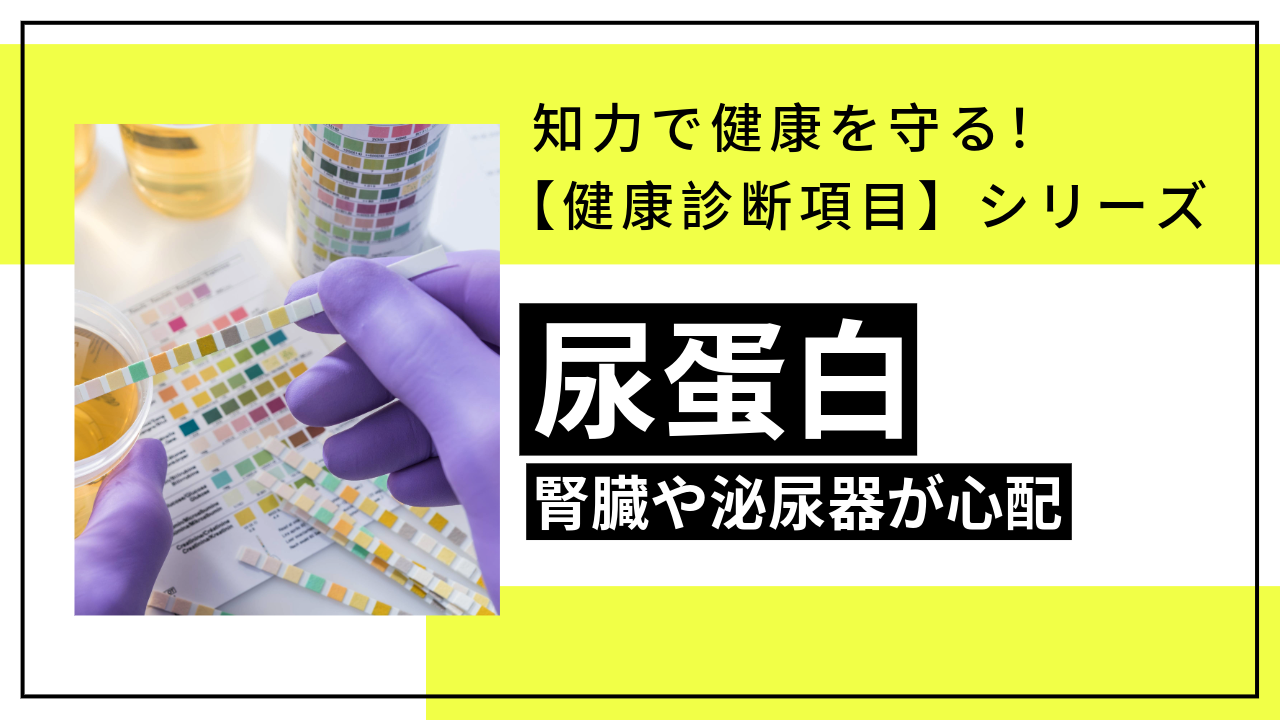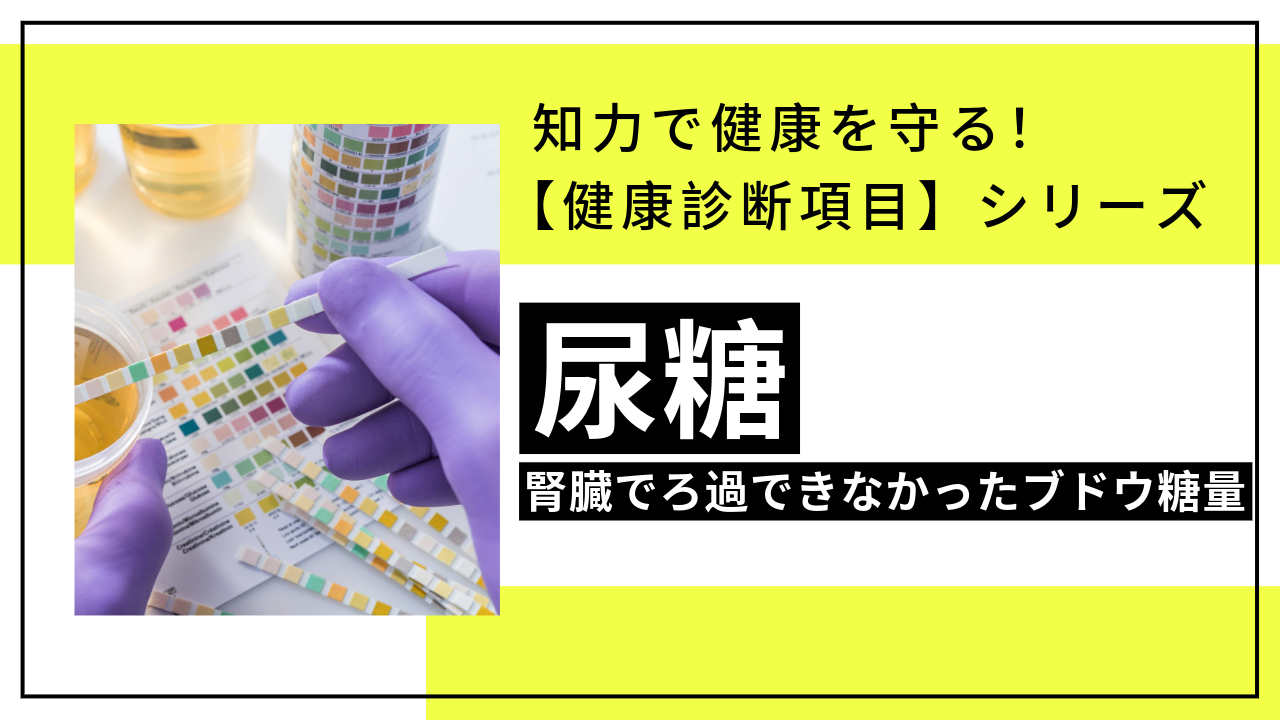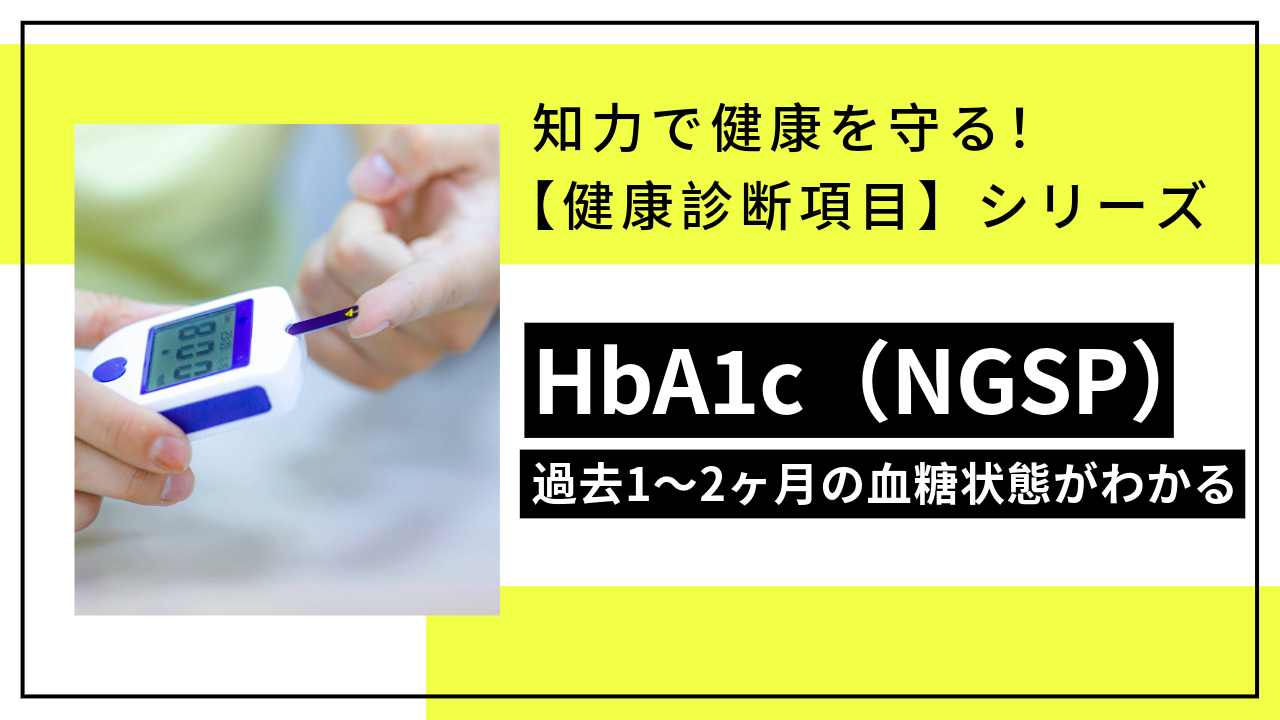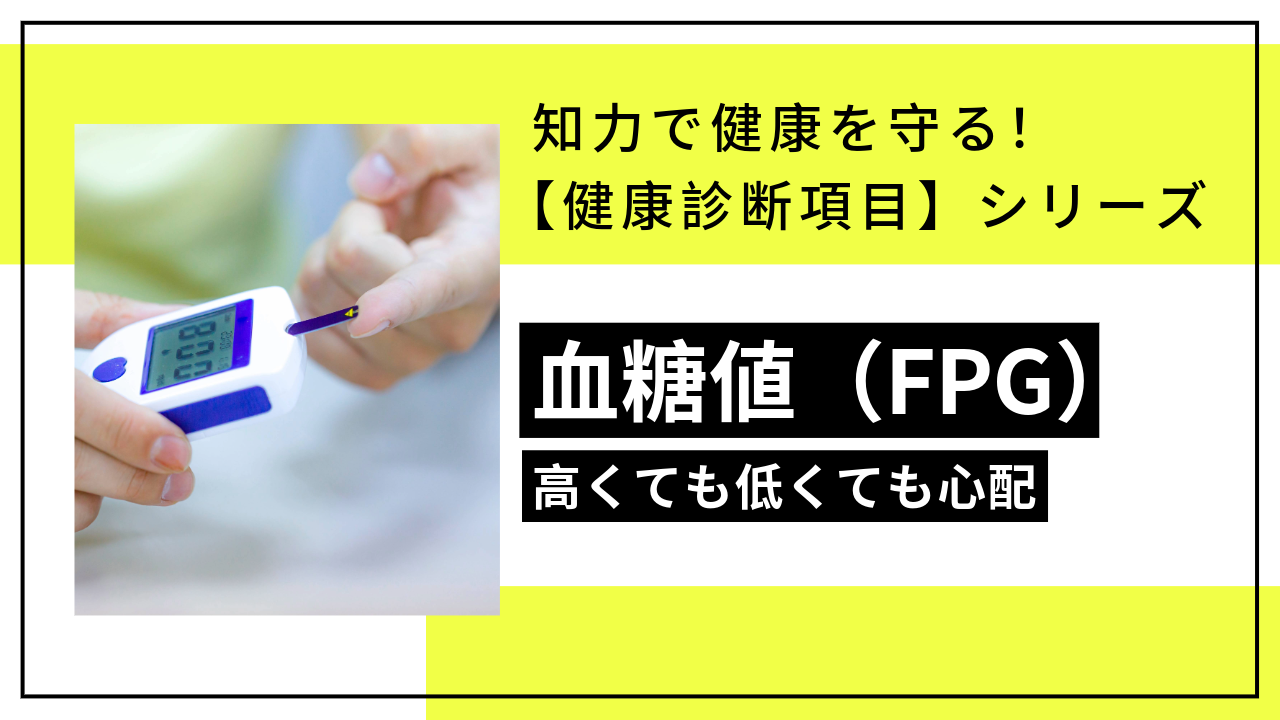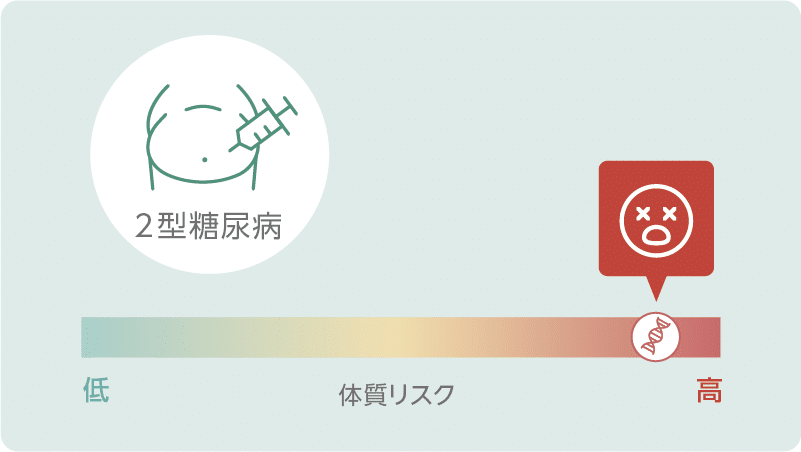【2型糖尿病】要注意健康診断項目とその他の検査方法
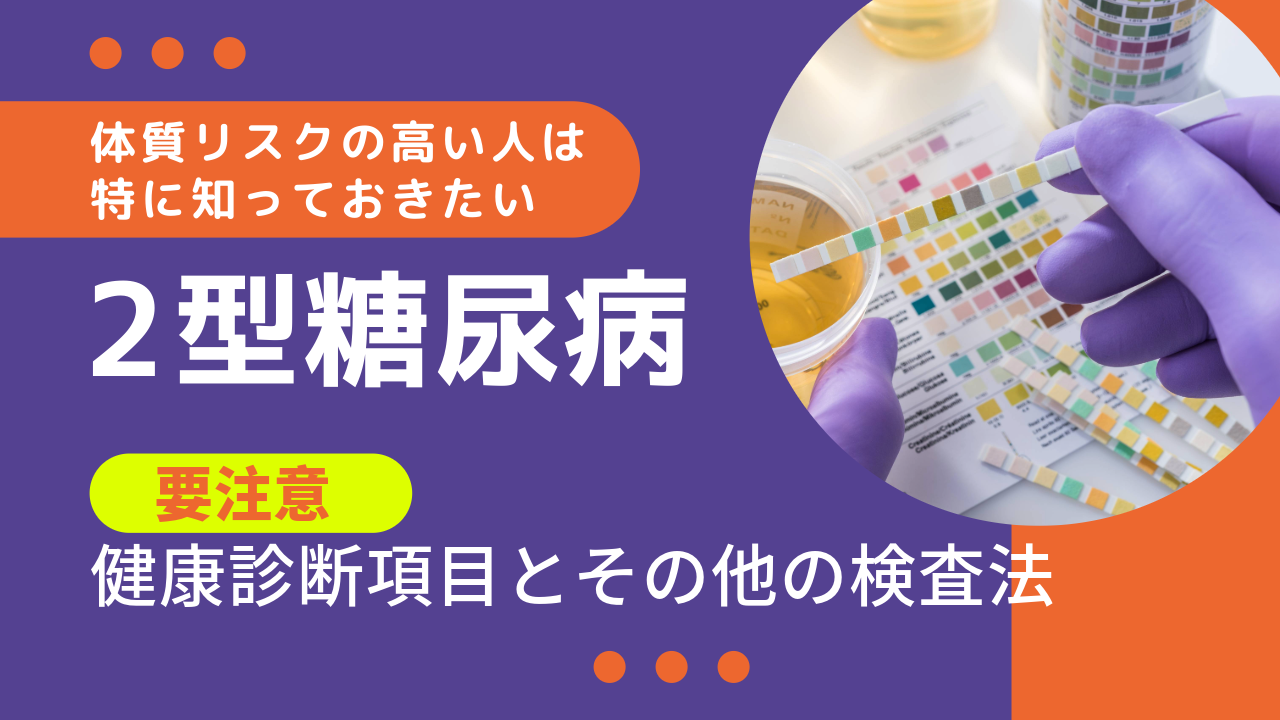
【2型糖尿病】に関連する健康診断の項目について
糖尿病とは、血液中のブドウ糖の濃度が高くなりすぎている病気のことです。高血糖の血液は血管に大きなダメージを与えるため、動脈硬化につながります。糖尿病が進行すると、脳卒中や網膜症、腎症、神経障害などのリスクも高まります。
ここでは、2型糖尿病の早期発見につながる健康診断の検査について解説します。
1. 血液検査
血液検査で「HbA1c(NGSP)」「血糖値(FPG)」の値を確認し、下記の基準値を超えると糖尿病と診断されます。
| 正常値 | 要注意 | 異常値 | |
| HbA1c(NGSP) | 5.5%未満 | 5.5%未満 | 5.5%未満 |
| 血糖値(FPG) | 99mg/dl 以下 | 100~125mg/dl | 126mg/dl 以上 |
HbA1c(NGSP)とは、血液中に含まれる糖化ヘモグロビンの割合のことです。赤血球の中にあるヘモグロビンは、血液中のブドウ糖と結合して糖化ヘモグロビンに変化します。ブドウ糖の量が多いほど糖化ヘモグロビンの数が多くなるため、糖尿病の判断基準として有効です。また、ヘモグロビンの寿命は120日間のため、瞬間的な血糖値ではなく、長期間の血糖値の高さを把握できます。
血糖値(FPG)は、空腹時に血液中に含まれるブドウ糖の量のことです。私たちの体はブドウ糖をエネルギーにしているため、活動している中で血液中のブドウ糖を消費します。そのため、空腹時の血糖値はある一定の数値まで下がっていくのですが、糖尿病の場合はブドウ糖が多くなっているため空腹時であっても血糖値は高くなります。
1回の血液検査で「HbA1c(NGSP)」「血糖値(FPG)」のどちらも測定できます。
血糖値についてもっと詳しく→
HbA1cについてもっと詳しく→
2. 尿糖
尿糖とは、尿の中に含まれるブドウ糖のことです。血液は腎臓でろ過され、ブドウ糖やタンパク質といった必要な成分は再吸収されます。通常ブドウ糖も再吸収されるため尿には含まれません。しかし、腎臓で一度に再吸収できるブドウ糖の量は決まっているため、血糖値が高い人は尿糖が確認されます。
尿糖の検査基準は、以下の通りです。
| 正常値 | 要注意 | 異常値 | |
| 尿糖 | (-) | (±) | (+) 尿糖(2+) 尿糖(3+) |
| 空腹時血糖 | 110mg/dl未満 | 110~126mg/dl未満 | 126mg/dl以上 |
尿糖の検査結果は(-)や(+)といった記号で表示されます。検査結果によるおおよその空腹時血糖が定められているため、尿糖から血糖値の高さを確認できます。
3.BMI(肥満度指数)
BMI(体重[kg] ÷ 身長[m]²)は、肥満度を示す指標です。肥満は、糖尿病のリスクを高めます。BMIが適正範囲に収まるよう、バランスの取れた食事や適度な運動を心がけましょう。
| 正常値 | 異常値(肥満の目安) |
|---|---|
| 18.5〜24.9 | 25以上 |
参照元:厚生労働省e-ヘルスネット
2型糖尿病の法定健診以外の検査
法定健診とは、労働安全衛生法で義務付けられている健康診断のことです。法定健診以外の糖尿病に関連する検査は下記の通りです。
- 75g OGTT(75グラム経口ブドウ糖負荷試験)
- グリコアルブミン
- CGM(Continuous glucose monitoring)持続血糖測定
- インスリン
- Cペプチド
それぞれの検査の詳細を解説します。
75g OGTT(75グラム経口ブドウ糖負荷試験)
75グラム経口ブドウ糖負荷試験とは、病院でブドウ糖を摂取して血液検査をするというものです。10時間以上空腹の状態で病院に行き、75gのブドウ糖が含まれたソーダ水を飲みます。ソーダ水を飲んで血糖値が上がったところを採決し、血糖値の上昇を確認します。
糖尿病の診断に有効で、糖尿病の境界型の判別にも使用されます。
グリコアルブミン
グリコアルブミンは、血液検査によって2週間の血液の状態を把握できる検査です。血液中にはアルブミンと呼ばれるタンパク質が流れており、ブドウ糖と結合してグリコアルブミンになります。2週間の寿命があるため、血液の2週間の状態を把握するために使用されます。
HbA1c(NGSP)と同じように、血液中のグリコアルブミンの割合によって糖尿病かどうかの判断をします。
CGM(Continuous glucose monitoring)持続血糖測定
CGM持続血糖測定は、24時間の血糖値の様子を測定するものです。皮下に細いチューブを入れ、5分おきに血糖値の測定が行われます。これを24時間継続することで血糖値の急な上昇などが確認できるため、隠れ糖尿病を見つける手法として有効です。
インスリン
血液検査によって、血中のインスリンの量を測定することができます。インスリンはブドウ糖を分解するホルモンのことです。糖尿病の多くがインスリンが不足している「分泌低下」や、インスリンが適量出ているのにブドウ糖が分解されない「インスリン抵抗性」であることがわかっています。
糖尿病の根本原因を探るために検査します。
Cペプチド
Cペプチドはインスリンと一緒にすい臓から分泌されるタンパク質です。Cペプチドの量を調べることですい臓でどのくらいのインスリンが分泌されたかが確認できます。血糖値が上がっている原因がインスリンの分泌量が減っていることかどうかがわかります。
Cペプチドの量が減っている場合、すい臓になんらかの異常が起きていてインスリンの分泌がうまく行われていないのだと判断できます。
2型糖尿病の法定健診以外の検査を受ける方法
2型糖尿病の法定健診以外の検査を受けるには、医療機関で医師の診察を受け、必要に応じた紹介や指示を受けることが一般的です。
または、特定の医療機関で人間ドックを申し込む方法もあります。検査内容によって追加費用が必要になり、場合によっては高額になる可能性もあるため注意が必要です。
健康診断などにより2型糖尿病が高いと判断された場合、精密検査を受けることで健康状態をより詳細に把握できます。気になる方は、かかりつけの医師に相談してみてもよいでしょう。