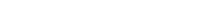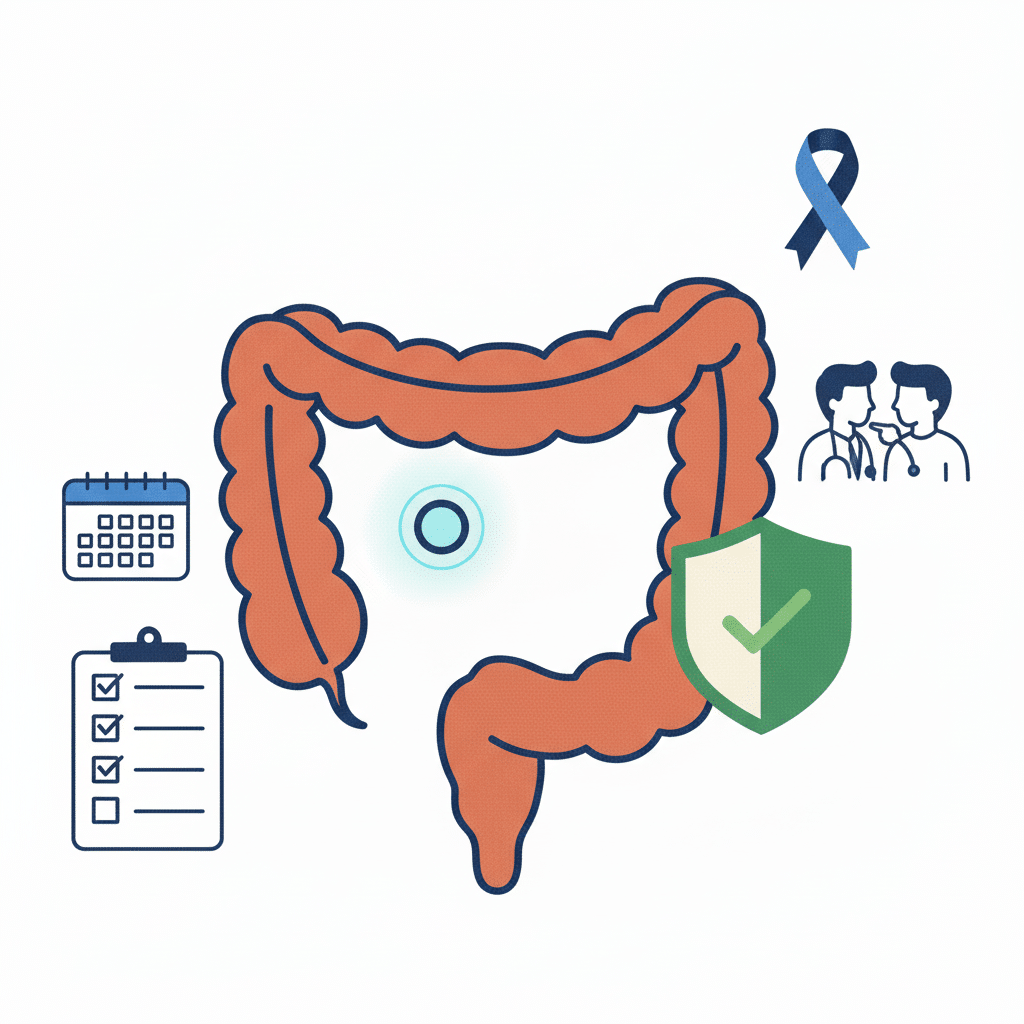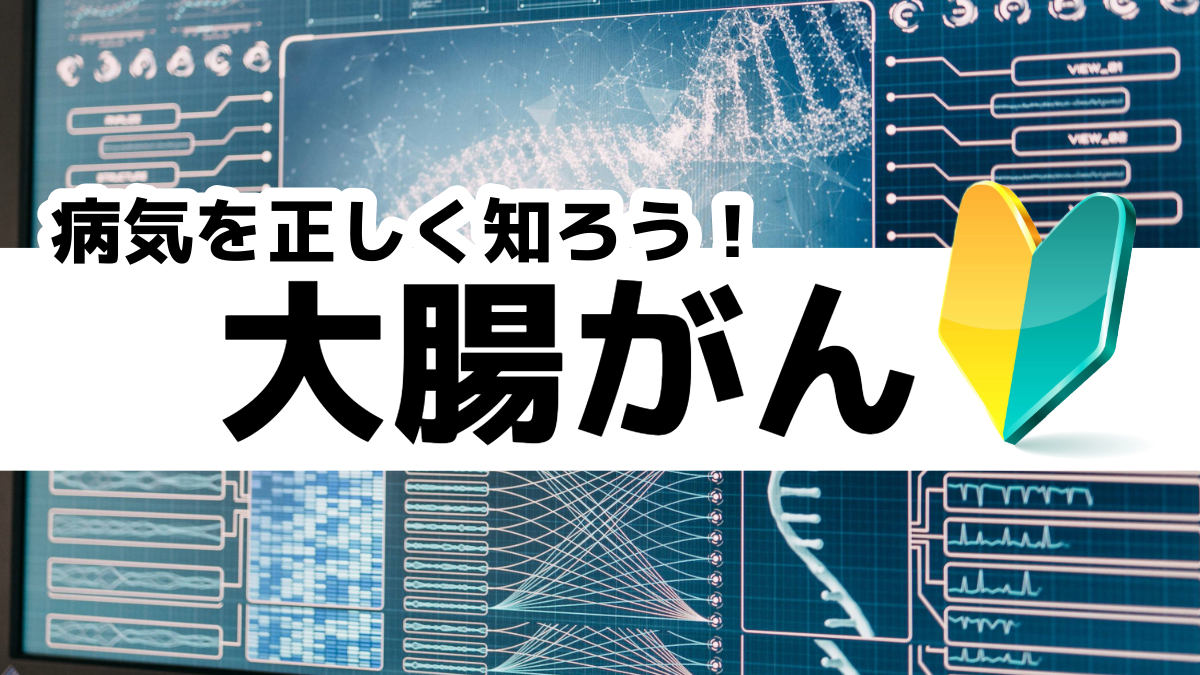【大腸がん】要注意健康診断項目とその他の検査方法

大腸がんに関連する健康診断の項目
大腸がんとは、大腸にできた悪性腫瘍のことです。大腸にできた良性ポリープががん化してしまうものと、大腸の粘膜が直接がん化してしまうものの2種類があります。
食生活の欧米化により、大腸がん罹患者は増加しています。特に40代以上になると大腸がんになりやすいことから、特定健康診に診断項目が追加されています。
ここでは、健康診断で実施される検査について解説します。
1. 便潜血
便潜血とは、採取した便にヒトヘモグロビンが含まれているかどうかを調べる検査です。1日法と2日法の2種類があり、1日法は1日に2度便を採取する方法で、2日法は2日に分けて2度便を採取する検査方法です。2日法の方が精度が高いです。
大腸がんやポリープができていると、排便時に便と大腸がんなどがこすれて、目視では確認できない血液が混じります。便潜血検査ではヒトヘモグロビンを検出するため、微量な血液にも反応を示し、大腸がんの早期発見に有効です。特に、大腸がんやポリープは痛みなどの初期症状がないため気付きにくい疾患なので、40歳以上の法定健診の検査項目に含まれています。
便潜血の判定は、以下の通りです。
| 異常なし | 異常 |
| 2日とも(-) | 1日でも(+) |
1日でも便潜血が確認出来たら異常と判断されます。
2.BMI(肥満度指数)
BMI(体重[kg] ÷ 身長[m]²)は、肥満度を示す指標です。肥満はがんのリスクを高めます。BMIが適正範囲に収まるよう、バランスの取れた食事や適度な運動を心がけましょう。
| 正常値 | 異常値(肥満の目安) |
|---|---|
| 18.5〜24.9 | 25以上 |
参照元:厚生労働省e-ヘルスネット
大腸がんの法定健診以外の検査
便潜血が陽性の場合、法定健診(労働安全衛生法で義務付けられている健康診断)以外の精密検査を受ける必要があります。
大腸がんに関連する法定健診以外の検査は下記の通りです。
- 全大腸内視鏡検査
- 大腸CT検査(CTC検査)
- 注腸造影検査
- PET検査
- 腫瘍マーカー検査
それぞれの検査の詳細を解説します。
全大腸内視鏡検査
内視鏡を肛門から挿入し、大腸全体を目視確認する検査が全大腸内視鏡検査です。肛門から盲腸まで大腸全体を確認するため、ポリープや大腸がんの可能性がある腫瘍が見つけられます。また、ポリープが見つかった場合は内視鏡を使って周辺の組織を採取して、病理診断されます。ポリープが良性かがん化しているかどうかを判断できるため、便潜血が陽性だった場合に行われる検査の一つです。
内視鏡を使えば、病変部を100倍に拡大して確認できるだけでなく、小さいポリープや大腸の粘膜表面にできたがんであれば内視鏡で切除可能です。
大腸CT検査(CTC検査)
大腸CT検査は、X線を当てて体の内部構造を書き出す手法です。水分、骨、脂肪、空気によってX線の吸収率が異なるので、内臓の造形把握に適しています。連続で何枚も写真を撮ることで、大腸がどのような形をしているかが立体で把握できます。
実際にポリープがどの辺りにあるかまで把握できるため、便潜血が陽性になった人の精密検査として利用されます。専門の機械に横たわるだけでよいので、全大腸内視鏡検査よりも体への負担が少ない検査です。
注腸造影検査
大腸CT検査をよりわかりやすくする検査が、注腸造影検査です。X線検査を受ける前に、肛門からバリウムと空気を送り込んで、大腸の中を満たします。その状態でX線を当てることで、大腸の形や良性ポリープや大腸がんの位置、狭くなっている場所なども細かくわかります。
直腸内にバリウムを入れることから、検査前日から検査食や下剤を飲む必要があり、当日も2Lの水や下剤を飲むことになります。体に負担が大きい検査ではありますが、大腸CT検査よりも正確にポリープや大腸がんの位置を把握できます。
CTコロノグラフィー
肛門から炭酸ガスを注入してCT検査を行うのが、CTコロノグラフィーです。注腸造影検査よりも体への的負担が少ないため、利用されることが多くなっています。炭酸ガスで腸内を満たすことで良性ポリープや大腸がんの正確な位置、大腸の狭い部分などが把握できる手法です。
PET検査
がん細胞がどこにあるかを確認するために利用されるのがPET検査です。がん細胞は増殖するのが速いため、多量のブドウ糖を必要とします。微量の放射線同位元素を含んだブドウ糖(FDG)を注射し、全身の断面撮影を行います。体のどの辺りでブドウ糖が使われたかを確認し、がん細胞がある臓器把握に適しています。
主に転移や再発を確認するために利用される検査ですが、ポリープが大腸がんになっているかを把握できる手段の一つです。
腫瘍マーカー検査
腫瘍マーカーとはがん細胞が増殖するときに発生する成分で、体内にがんがある場合は腫瘍マーカーが体内に増えています。血液検査や尿検査によって確認できるため、体への負担は少ないです。
大腸がんである可能性が高い場合に受けることが多い検査です。
大腸がんの法定健診以外の検査を受ける方法
大腸がんの法定健診以外の検査を受けるには、医療機関で医師の診察を受け、必要に応じた紹介や指示を受けることが一般的です。特に、便潜血が陽性の場合はかかりつけの医師に相談することで、精密検査が受けられる病院の紹介をしてもらえます。
便潜血が陽性だったからといって、必ずしも大腸がんであるというわけではなく、良性のポリープなどが原因のこともあります。良性であってもポリープががん化することは少なくないため、定期的に精密検査を受けることで、大腸がんの早期発見につながるでしょう。
費用は検査内容によって異なり、場合によっては高額になる可能性もあるため注意が必要です。