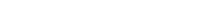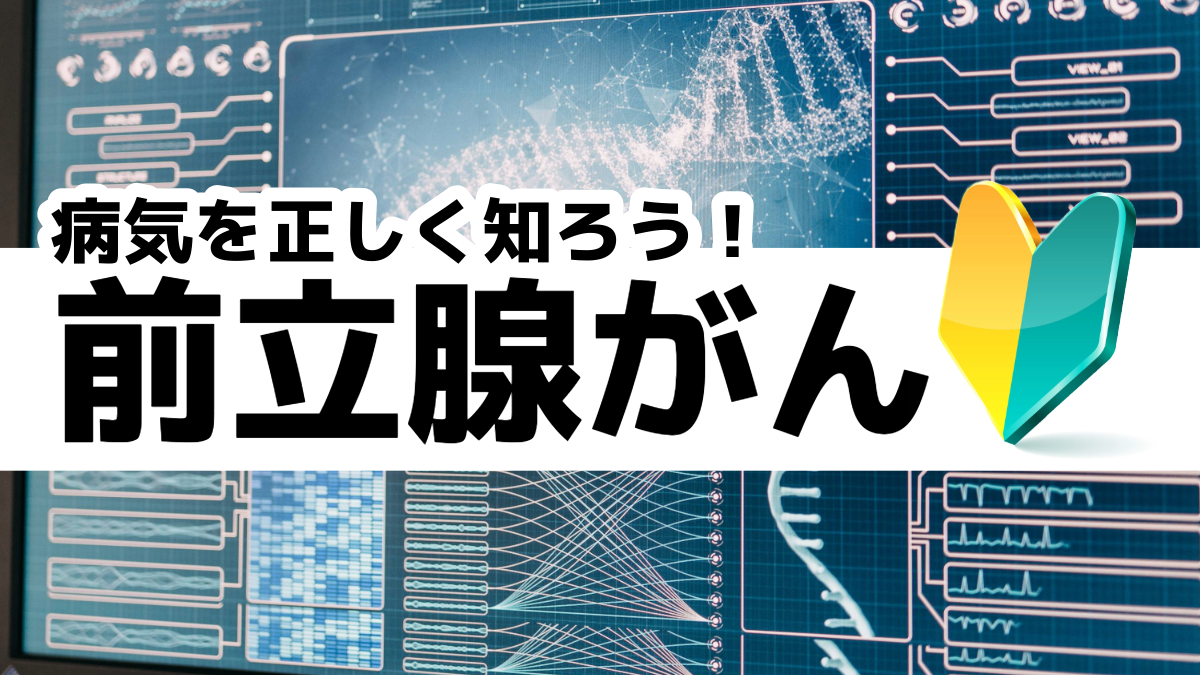【前立腺がん】要注意健康診断項目とその他の検査法
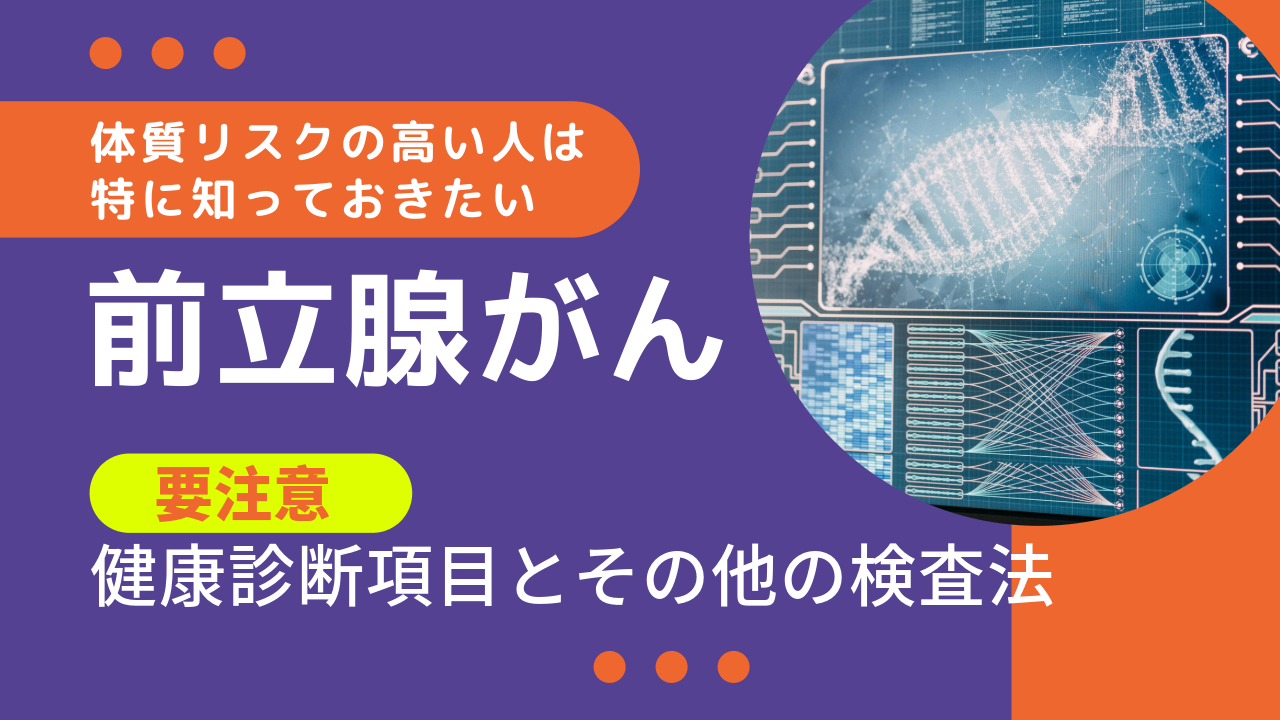
前立腺がんに関連する健康診断項目
厚生労働省は、市町村が科学的根拠に基づいてがん検診を実施できるよう、ルールを策定していますが、前立腺がん検診に関しては、明確な基準が示されていないのが現状です。1 前立腺がんの検査は後述の「その他の検査」をご参照ください。
健康診断では、前立腺がんの発症リスクや早期発見のため「BMI」にご注意ください。
BMI(Body Mass Index:体格指数)は、体重と身長をもとに算出される値で、一般的に肥満かどうかを判断する目安となります。
数値は、体重(kg)を身長(m)の二乗で割って求められます。
BMIが30以上の肥満の場合、悪性度の高い前立腺がんのリスクが高まることがわかっています。
BMIの正常値と異常値
BMIの正常値と異常値は以下の通りです。
| 分類 | BMI |
|---|---|
| 低体重 | 18.5未満 |
| 標準体重 | 18.5〜24.9 |
| 肥満1 | 25.0以上30.0未満 |
| 肥満2 | 30.0以上35.0未満 |
| 肥満3 | 35.0以上40.0未満 |
| 高度肥満 | 40.0以上 |
参照:一般社団法人日本肥満学会「肥満症診療ガイドライン2022」
BMIについてもっと詳しく→
その他の検査
前立腺がんには、以下のような検査があります。
- PSA検査(血液検査)
- 直腸診
- MRI検査
- 前立腺生検
この検査でわかること
PSA検査(血液検査)
PSAは「前立腺特異抗原」と呼ばれるたんぱく質で、前立腺から分泌されます。この値は前立腺がんの初期段階から上昇するため、がんを早期に発見するのに役立ちます。
PSA検査は特に40歳以上の男性に推奨され、50歳を超えた男性においては毎年の定期的な検査が勧められています。
PSA検査の正常値は、「4.0ng/mL以下」ですが、年齢によって基準値が少し異なります。2
- 50〜64歳:3.0ng/mL以下
- 65〜69歳:3.5ng/mL以下
- 70歳以上:4.0ng/mL以下
年齢が上がるにつれて基準値が少しずつ高くなるのは、年齢とともに自然とPSAの値が増加するためです。
PSA値が10ng/mLを超えると、前立腺がんの可能性が高くなります。この場合、がんの有無を確認するために、さらに詳しい検査が必要です。
また、PSA値が100ng/mLを超えると、がんが転移している可能性が考えられるため、より詳しい検査を受ける必要があります。
ただし、基準値内でも前立腺がんが見つかることがあるため、少し高めの数値が出た場合は定期的な検査や経過観察が勧められます。
- 1.0ng/mL以下:3年ごとに検査を受ける
- 1.1ng/mL以上〜正常値以下:毎年検査を受けるのが望ましい
PSAの値を毎年確認することは、前立腺がんの早期発見や再発予防にも役立ちます。
PSAは、前立腺肥大や前立腺炎が原因で値が上がることもあります。
また、前立腺がんは初期症状がほとんどなく、次のような症状が現れることがありますが、他の疾患でも見られる場合があるため見分けがつきにくいです。
- 尿の出が悪い
- 尿の切れが悪い
- 残尿感がある
- トイレが近い
前立腺がんの可能性を見逃さないためにも、詳しい検査で総合的に判断することが重要です。
直腸診
直腸診は、前立腺がんを早期に見つけるための検査の一つです。前立腺がんは初期の段階では症状が出にくいため、この検査が診断に役立ちます。
検査は仰向けや体を少し前に曲げた状態で行います。医師が麻酔ゼリーを塗った指を肛門から挿入し、指で前立腺の位置、大きさ、形、硬さ、そして周囲との関係を確認します。
前立腺は、通常「クルミ大」「鶏卵大」などと表現されるサイズが基準です。
正常な場合はゴムのような弾力がありますが、硬さが強いほど悪性の可能性が高まります。
MRI検査
MRI(磁気共鳴画像法)は、前立腺がんがあるかどうかを予測するための検査です。
磁気を使って体の中を詳しく調べることができ、高精度な画像で前立腺の異常を確認します。
MRI検査の結果は、「PI-RADSスコア」という指標で評価されます。このスコアは、がんの可能性を5段階で表します。
| スコア | 判定 |
|---|---|
| 1点 | がんの可能性が極めて低い |
| 2点 | がんの可能性が低い |
| 3点 | どちらとも言えない |
| 4点 | がんの可能性が高い |
| 5点 | がんの可能性が極めて高い |
参照:日本泌尿器科学会「前立腺癌診療ガイドライン2023年版
この検査だけでがんかどうかを確定することはできませんが、生検(がんの有無を確認するための組織検査)が必要かどうかを判断する大切な手がかりになります。
前立腺生検
前立腺生検は、前立腺がんの確定診断を行うための唯一の方法です。
血液検査でPSAが基準値を超えた場合や、直腸診やMRI検査で異常が疑われる場合に行われ、がん細胞が存在するかを調べます。
検査の方法は以下の通りです。
- 肛門から超音波装置を挿入し、前立腺の様子を見ながら検査を進めます。
- 直径1.5〜2mmの細い針を複数箇所に刺し、前立腺組織を採取して顕微鏡で詳しく調べます。
最近では、超音波の画像にMRIの情報を組み合わせた「MRIガイド下生検」を行う医療機関も増えています。
この方法では、より正確にがんが疑われる部分を狙って検査ができるため、精度が高く、患者さんの負担も軽減されます。
検査後の注意点は以下の通りです。
- 検査は腰椎麻酔や全身麻酔で行われるため、検査後の安静が必要です。
- 生検後には、血尿や発熱、尿閉(尿が出にくくなる)といった合併症が起こる可能性があります。
多くの場合、入院して経過観察を行いますが、日帰りで検査を受けられる病院もあります。
この検査はどこで受ける?
泌尿器科やがん専門の医療機関で受けることができます。
もし家族に前立腺がんを患った人がいる場合、自分も前立腺がんのリスクが高くなる可能性があります。このような場合は、45歳頃からPSA検査を受けて健康状態を確認することが勧められます。
また、家族歴がない場合でも、40歳の時点でPSA値が基準値を超えている場合は、定期的に検査を受けることが望ましいです。