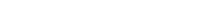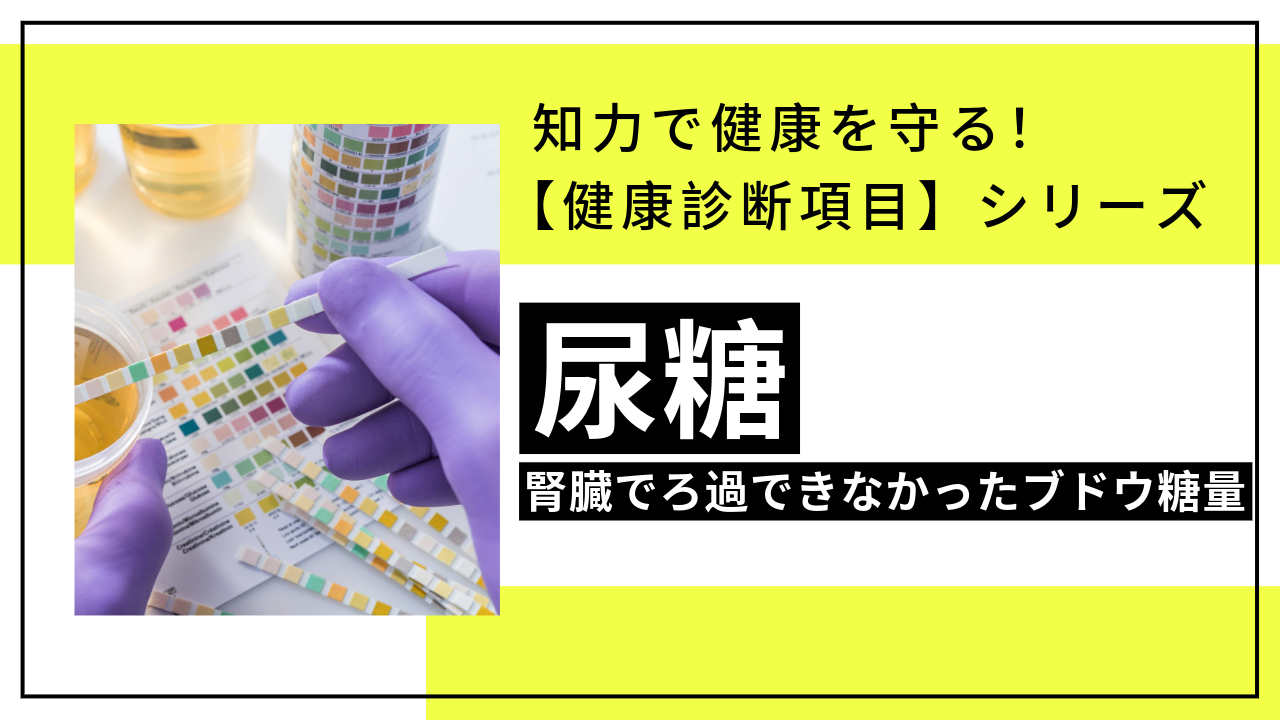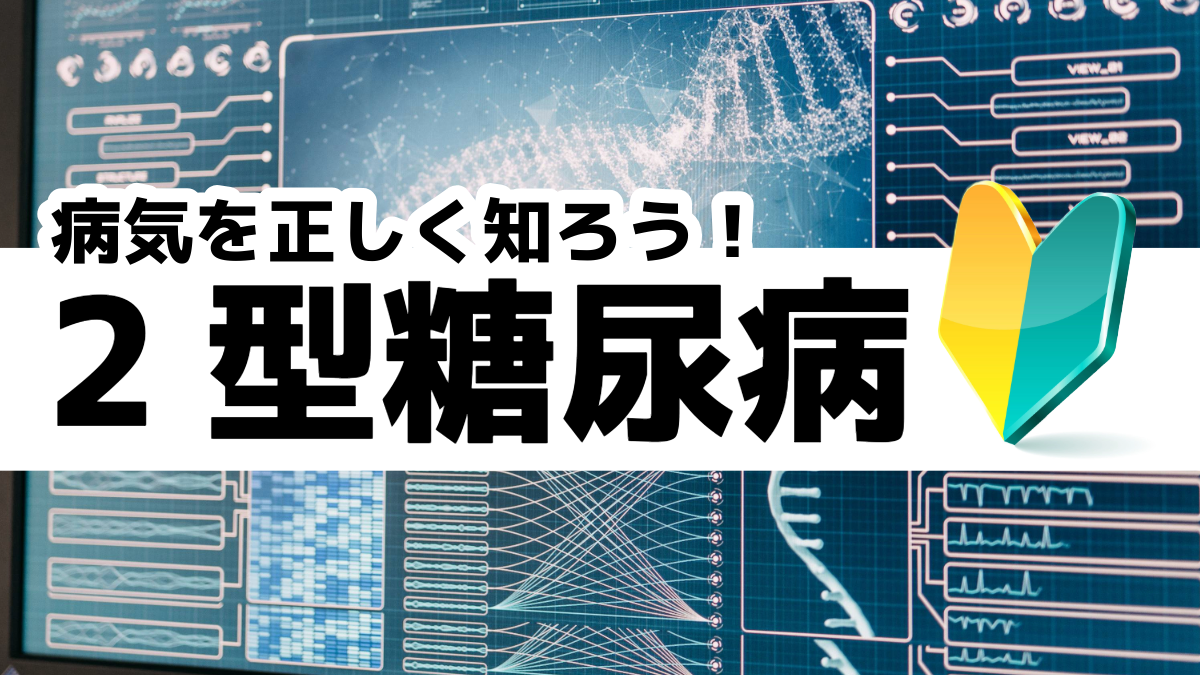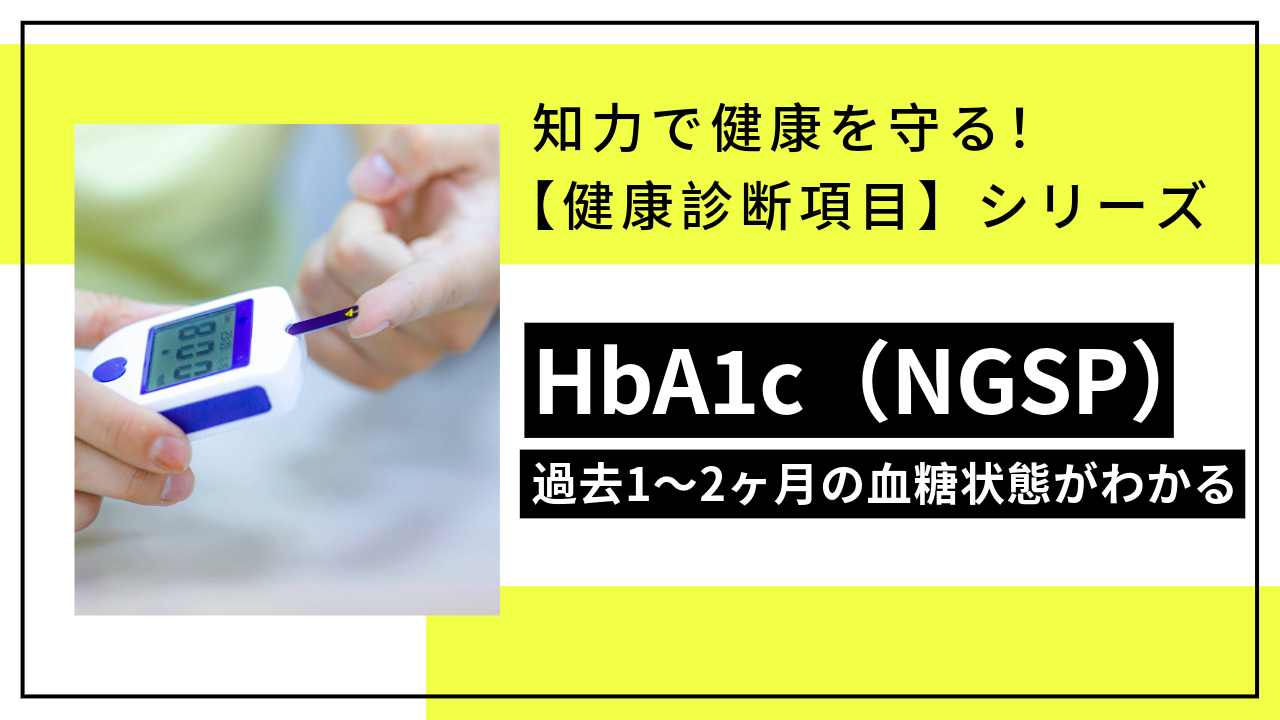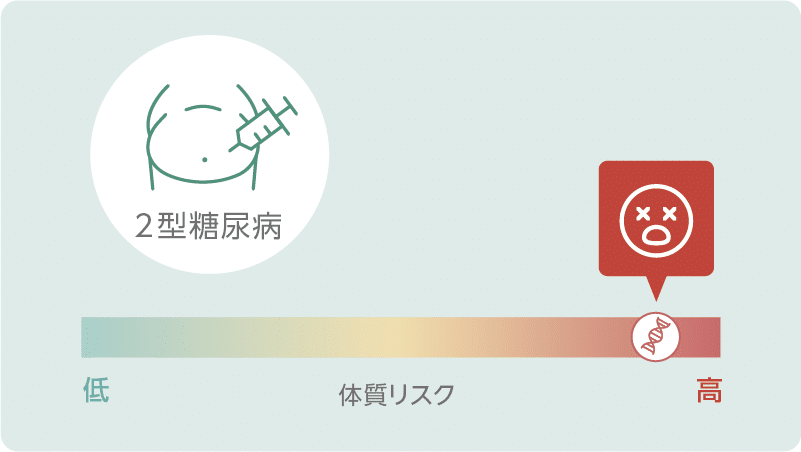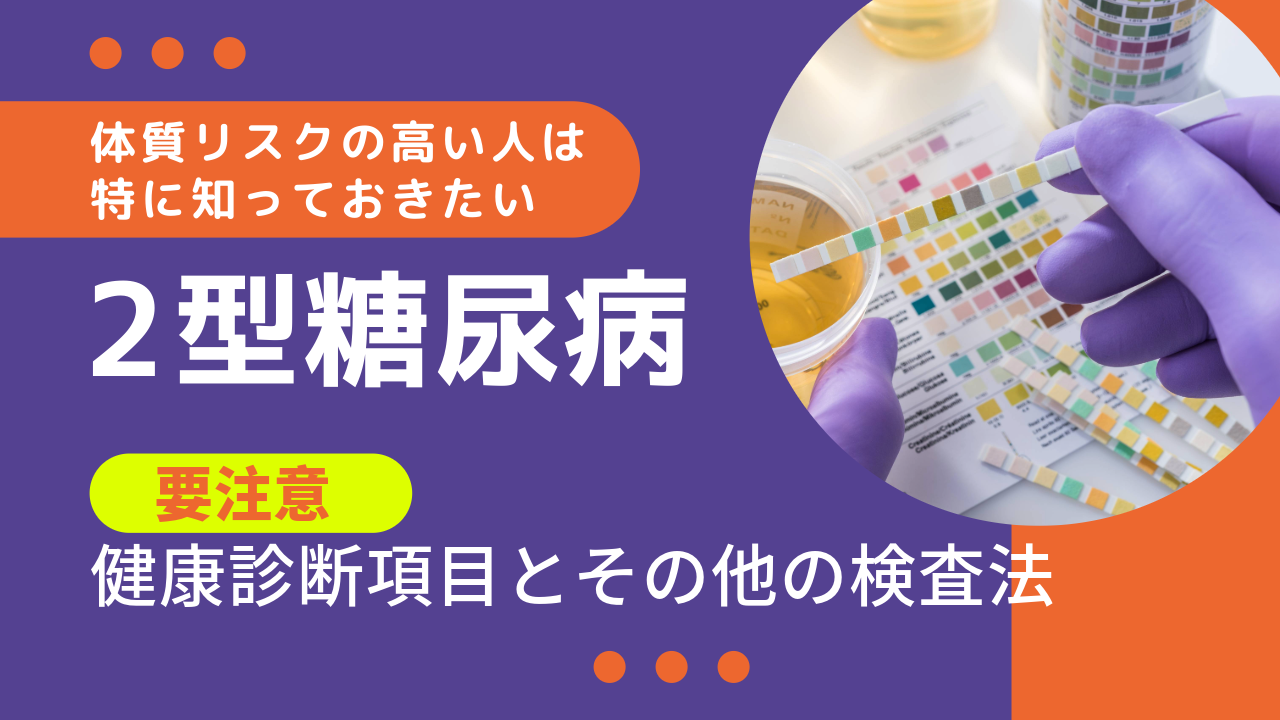【健康診断項目】尿蛋白(たんぱく)
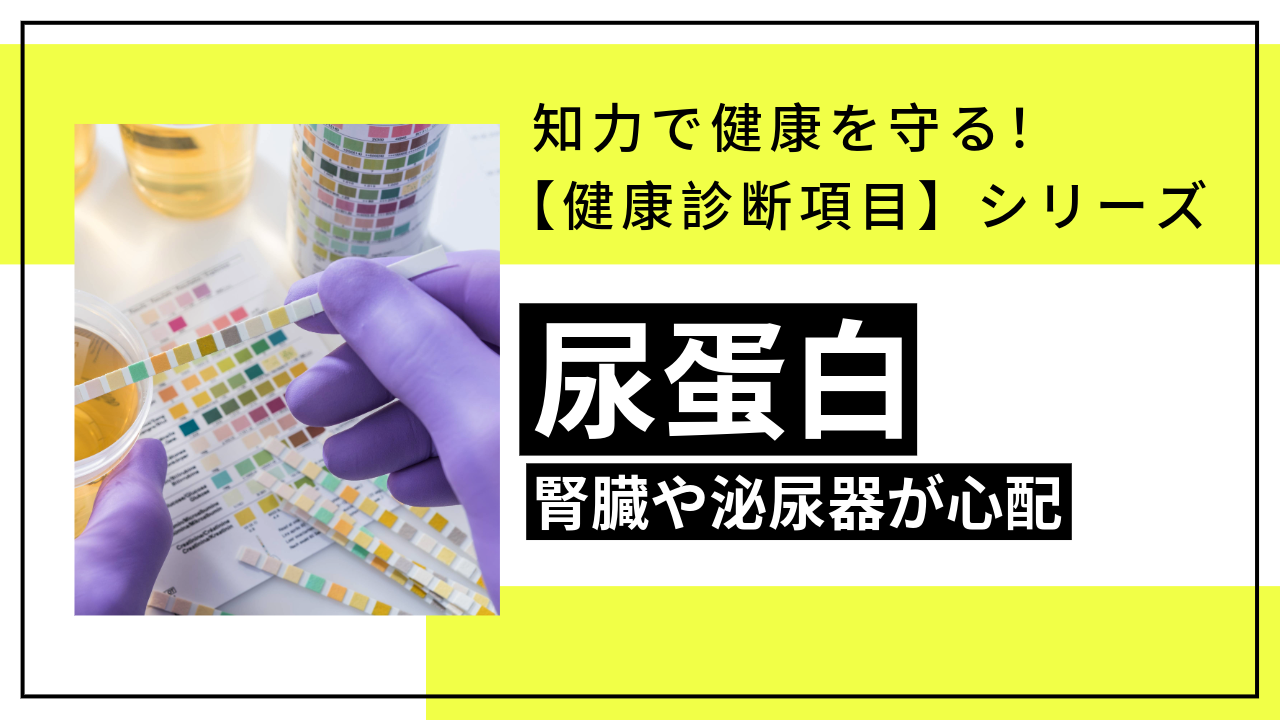
尿蛋白とは?
尿蛋白(にょうたんぱく)とは、尿の中に含まれるタンパク質のことです。尿にはもともと少量のタンパク質が含まれていますが、尿蛋白が過剰に排出されてしまうことがあります。
体の中の不要物を尿として排出する際、腎臓で血液をろ過します。タンパク質を含む必要な成分は、再吸収されて血液の中に戻っていき、不要な成分は尿として体外に排出される仕組みです。
しかし、腎臓や尿管などの泌尿器に異常が発生していると再吸収がうまく行われず、タンパク質が尿として排出されてしまいます。尿検査を行って尿蛋白の数値が高い人は、腎臓や泌尿器に何らかの異常が起きている可能性があると判断されます。
「尿蛋白」と似ている言葉に「蛋白尿」というものがあります。2つの言葉の違いは、以下の通りです。
- 尿蛋白:尿の中に含まれているタンパク質のこと
- 蛋白尿:タンパク質が多く含まれている尿のこと
健康診断で測定するのは尿中のタンパク質の量で、尿蛋白です。
正常値と異常値
尿蛋白の正常値と異常値は以下の通りです。
| 基準値 | 要注意 | 異常 |
| 陰性(-) 15mg/dl以下 | (+)(±) 15~30mg/dl | (2+以上) 30mg/dl以上 |
異常値が出たからといってすぐに腎臓の疾患や泌尿器の異常だと診断されるわけではありませんが、高い数値が続いてしまうと疾患リスクが高まります。
異常値だとどうなる?
尿蛋白の量が増えると尿の粘度が上がるため、排尿時に泡立ちが目立つこともありますが、それ以外では気づきにくいです。尿蛋白になってもほとんどの場合、自覚症状はありません。
しかし、通常排出されないタンパク質が過剰に尿に含まれている状態なので、腎臓や糸球体の疾患リスクが高まります。腎臓病は自覚症状が少なく、発覚すると病状が進行してしまっていることが多い疾患です。放置しすぎると最終的には透析を受けなければいけない状況に陥ることもあります。
最近では肥満や高血圧といった生活習慣病からなる慢性腎臓病(CKD)が増加しています。慢性腎臓病(CKD)は、腎臓の機能が低下している状態が続いている状態のことで、心筋梗塞や脳卒中などの危険因子とされています。
尿蛋白の異常値は、放置してしまうと非常に危険な疾患につながってしまうので注意しましょう。
異常値の原因は?
尿蛋白の異常値が出てしまう原因は、以下の通りです。
タンパク質の過剰摂取
タンパク質を過剰摂取していると、血液中のタンパク質の量も増えます。腎臓の働きで再吸収できる量は決まっているので、タンパク質を過剰摂取している人は一時的に尿蛋白の量が増えてしまうことがあります。「生理的たんぱく尿」とも呼ばれていて、過剰なダイエットや筋肉トレーニングのためにタンパク質をとりすぎている人に起きやすいです。
生活習慣病による慢性腎臓病(CKD)
慢性腎臓病(CKD)は、腎臓の機能が低下している状態が3カ月以上続ている状態のこと。腎臓の機能が低下しているため、再吸収がうまく行われず尿蛋白増加の原因になります。
血糖値が高い・血圧が高い状態が続いていると血液のコントロールを行っている腎臓に大きな負担を与えるため、慢性腎臓病(CKD)になりやすいです。特に、糖尿病、高血圧、肥満の人は注意が必要です。
急性糸球体腎炎や慢性糸球体腎炎
腎臓の中で尿を作っている「糸球体」という器官が炎症を起こしている状態を、糸球体腎炎といいます。病原菌によって炎症が起きることを急性糸球体腎炎、遺伝や生まれつきの疾患で性糸球で炎症が起きていて緩やかに腎臓の機能が低下している状態を慢性糸球体腎炎といいます。
糸球体腎炎の場合は、健康診断の数値などが急に(3+)や(4+)といった異常値を出しますので、気づきやすいです。異常値が確認された場合は速やかに医療機関に相談しましょう。
その他の原因
疾患以外で、尿蛋白が出てしまう原因には以下のようなものがあげられます。
- ストレス
- 疲労
- 睡眠不足
- 水分不足
- 妊娠中
これらの原因はあくまで一時的な尿蛋白の異常値につながる原因です。継続的に異常値が出てしまう場合は、別の原因の可能性が高いです。
正常値でいるために
腎臓に負担を与えないように血糖値や血圧の管理を行うことが近道です。尿蛋白の異常値が出てしまう人の多くが生活習慣病になりやすい生活を送っていることが多いため、生活習慣の見直しを行いましょう。
- 食べ過ぎに気を付ける
- アルコールの飲み過ぎに気を付ける
- 適度な運動を行う
- ストレスがかかりにくい生活を心がける
- 喫煙は控える
「日本人の食事摂取基準(2025年版)」には、高血圧予防のため食塩摂取量を1日あたり6g未満1に定めるようにと記載があります。まずは、食生活の見直しから、運動や喫煙などの生活習慣の改善を心がけてください。