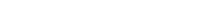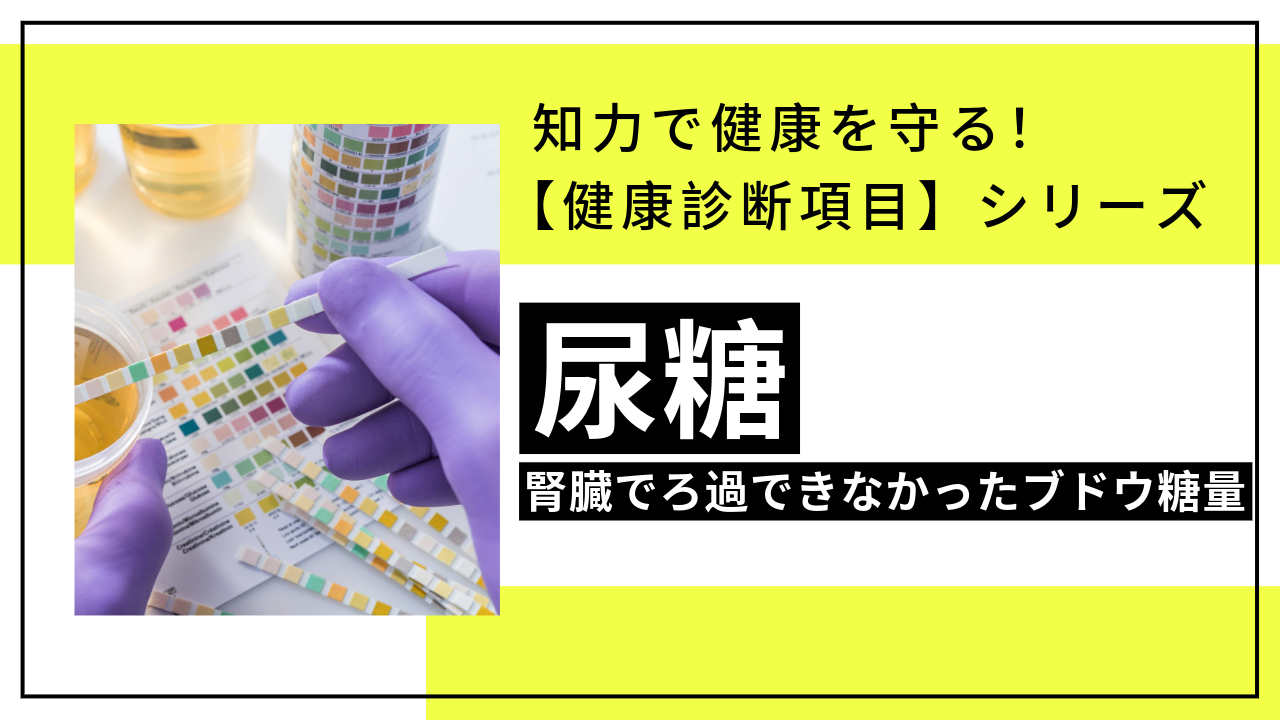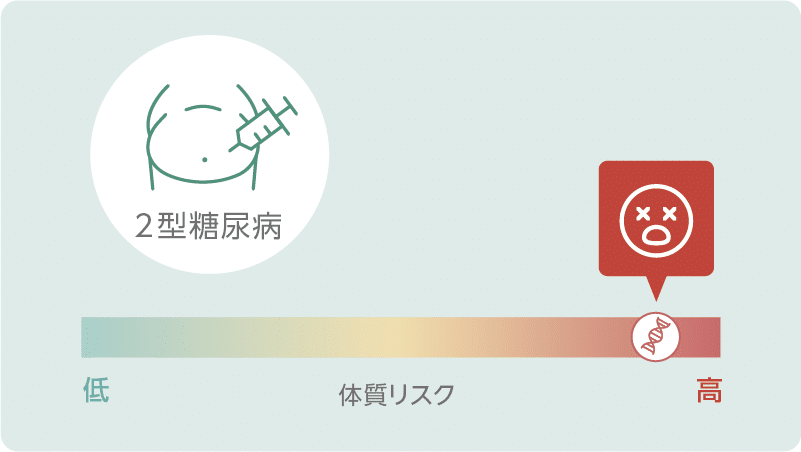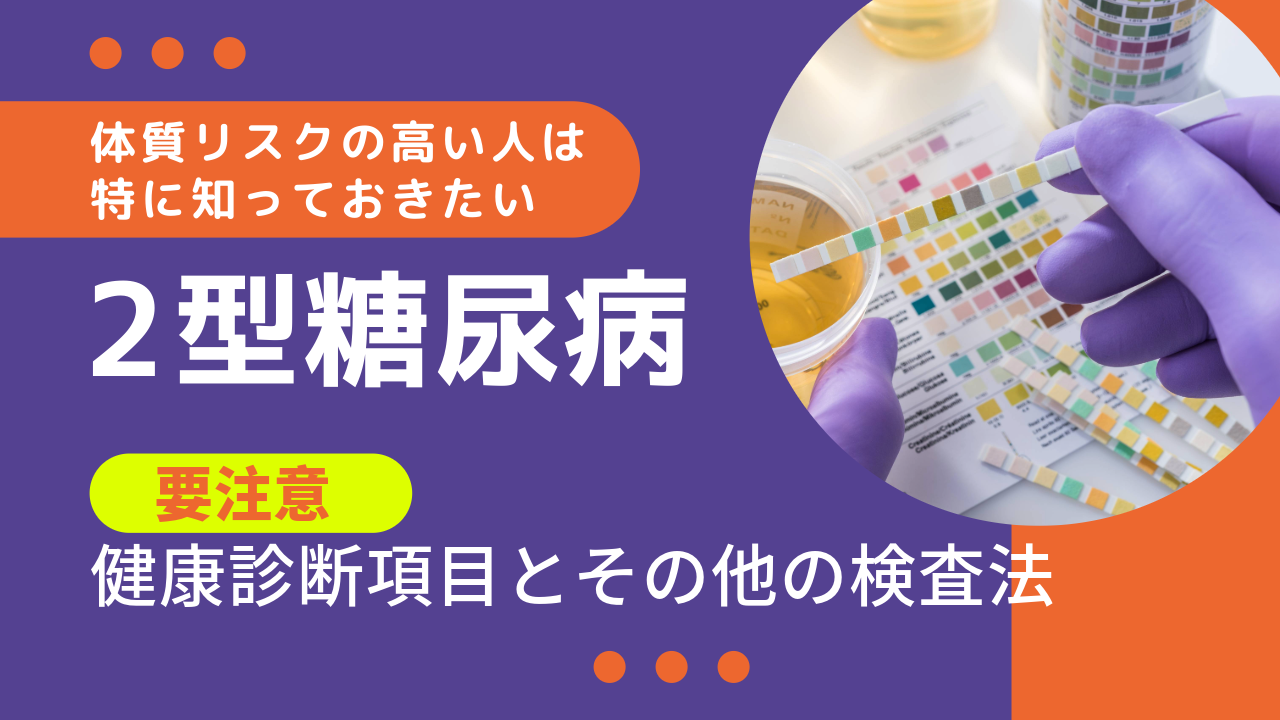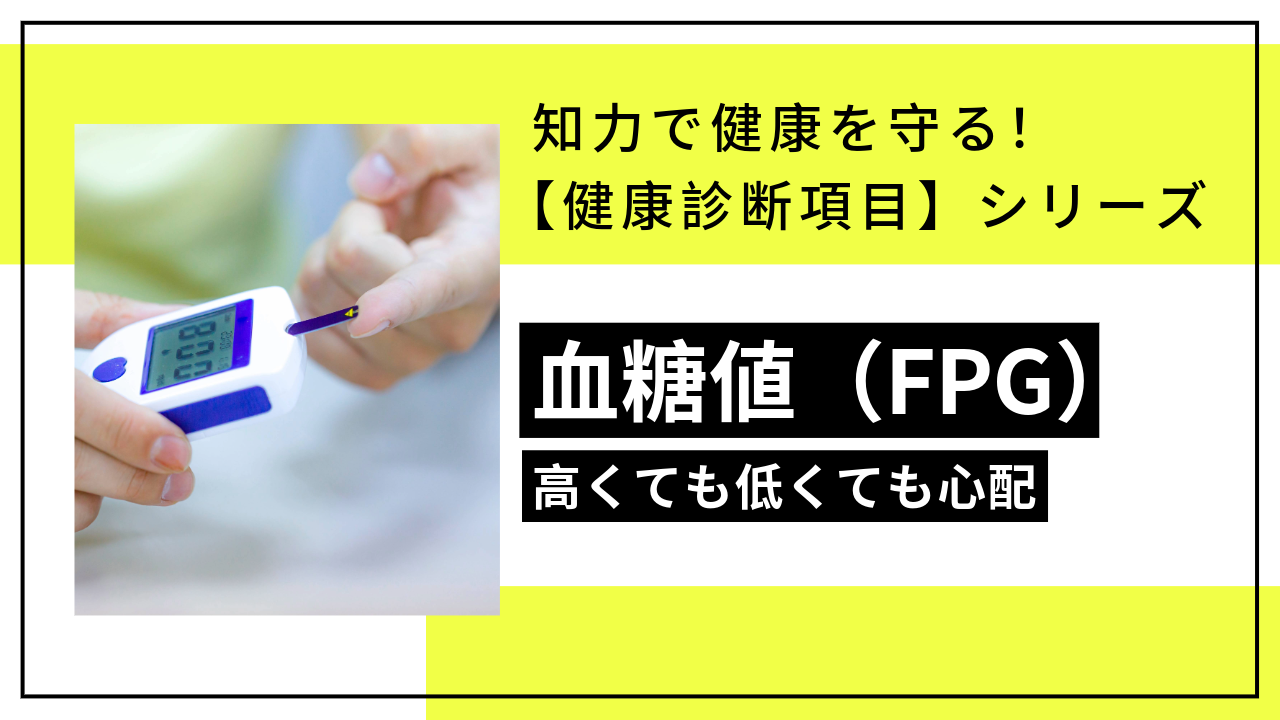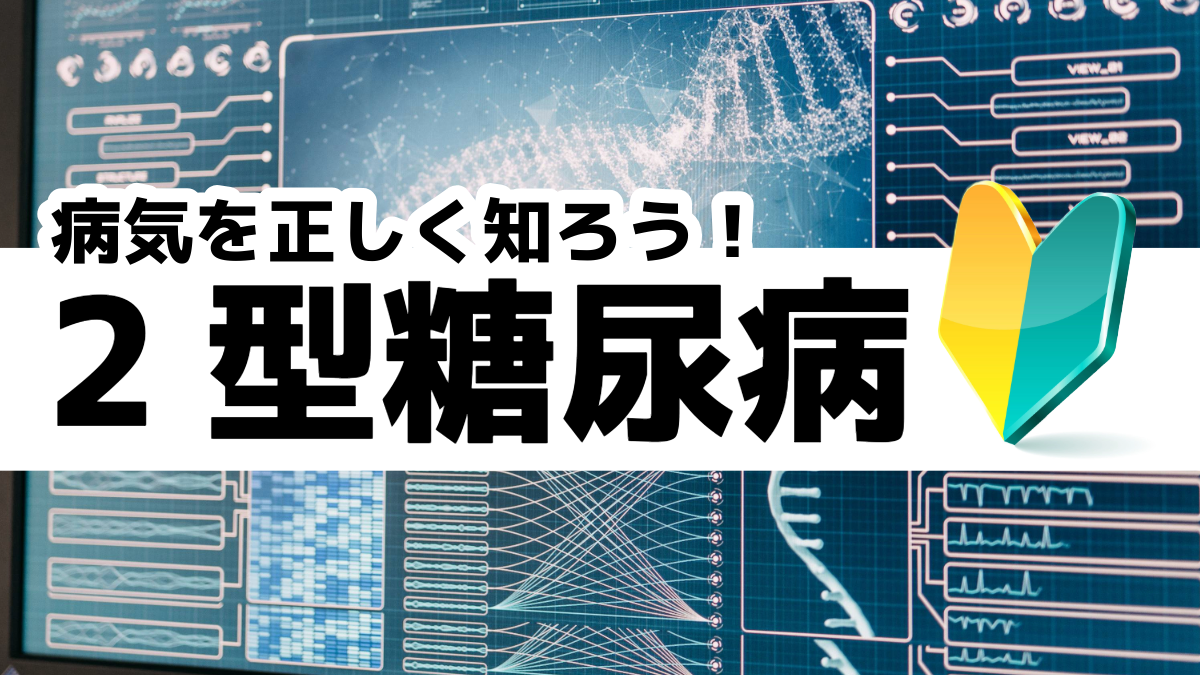【健康診断項目】万病の元となる「BMI」の異常値

BMIとは?
BMI(Body Mass Index:肥満度指数)は、健康管理において体格を評価するために広く用いられる指標です。
BMIは「体重(kg)÷身長(m)の2乗」で計算され、その数値によって肥満度や低体重を判定します。1
たとえば、体重60kgで身長1.6m(160cm)の人の場合、
60 ÷ (1.6 × 1.6) = 23.4となり、この「23.4」がBMIです。
BMIは体重と身長に基づく簡易的な計算であるため、筋肉量や骨格の影響を受けることがあり、体脂肪率とは異なる点に注意が必要です。
正常値と異常値
日本肥満学会の基準では、BMIの正常範囲は18.5〜24.9とされており、健康的な体重の目安です。異常値は以下のように分類されています。
| 分類 | BMI |
|---|---|
| 低体重 | 18.5未満 |
| 標準体重 | 18.5〜24.9 |
| 肥満1 | 25.0以上30.0未満 |
| 肥満2 | 30.0以上35.0未満 |
| 肥満3 | 35.0以上40.0未満 |
| 高度肥満 | 40.0以上 |
参照:一般社団法人日本肥満学会「肥満症診療ガイドライン2022」
また、WHO(世界保健機関)は、BMIが25以上を「過体重」、30以上を「肥満」と定義しており、日本の基準と少し異なります。
異常値だとどうなる?
BMIが正常範囲(18.5〜24.9)を超えたり下回ったりすると、健康にさまざまなリスクが生じます。
肥満の場合
生活習慣病のリスクが高まる
肥満になると、高血圧や糖尿病、脂質異常症、心臓病や脳卒中といった生活習慣病のリスクが大きく増加します。
特に日本人は、欧米人より低いBMIでも病気になることが多いとされています。
がんのリスクが高まる
BMIが30以上になると、大腸がんや乳がん、子宮体がんなどの特定のがんのリスクが上がることがわかっています。
肥満が続くと、体の中で慢性的な炎症が起きたり、ホルモンバランスが乱れたりすることが原因とされています。
関節への負担が増える
体重が増えることで膝や腰にかかる負担が大きくなり、変形性膝関節症や腰痛が起きやすくなります。
睡眠時無呼吸症候群になりやすい
体重が増えると、気道が狭くなって寝ている間に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群」になることがあります。
これにより、日中に強い眠気や集中力の低下が起きることがあります。
低体重(痩せ)の場合
糖尿病のリスクが高まる
低体重の人は、筋肉や脂肪が少ないため、血糖値を調整するインスリンが効きにくくなり、糖尿病になりやすいとされています。
標準体重の人と比べて、糖尿病のリスクが7倍になるというデータもあります。栄養をしっかり摂り、適度に運動をして筋肉を保つことが大切です。
がんのリスクが高まる
低体重では栄養不足により免疫力が低下します。
その結果、感染症にかかりやすくなるだけでなく、がん細胞を排除する力も弱まり、がんのリスクが高くなるとされています。
女性特有の健康問題が起きやすい
低体重の女性はホルモンバランスが乱れることで、生理が不規則になったり、排卵しにくくなったりすることがあります。
また、妊娠中には妊娠糖尿病や早産のリスクが高まり、赤ちゃんの発育にも影響が出ることがあります。
さらに、骨密度が低下して骨折しやすくなる「骨粗鬆症」のリスクも増加します。
異常値の原因は?
BMIが正常な範囲を外れる原因は、主に食事や生活習慣に関係しています。肥満と低体重の原因はそれぞれ異なります。
肥満の原因
肥満になる主な理由は、食べ過ぎや運動不足です。以下の習慣が原因になります:
- 食べ過ぎる習慣(お腹いっぱいになるまで食べる、残り物を無意識に食べる)
- 間食が多い(お菓子やジュースなど)
- 夜遅い時間に食事をする(午後9時以降に食べることが多い)
- 早食いや「ながら食い」(テレビやスマホを見ながら食べる)
これらの習慣は体に必要以上のエネルギーをため込む原因になります。その結果、余分なエネルギーが脂肪として体に蓄積され、肥満を引き起こします。
また、ストレスが原因で食べ過ぎてしまうこともあります。ストレスによる過食は精神的な影響もあるので注意が必要です。
低体重の原因
低体重になる理由の多くは、無理なダイエットや食事制限です。特に若い女性に多く見られます。
- 栄養バランスを考えずに極端に食事を減らす
- 「痩せたい」という気持ちから必要な栄養まで取らなくなる
これらの無理なダイエットは、体に必要な栄養が足りなくなり、健康に悪い影響を与えます。
また、食欲がない(食欲不振)や、胃腸の調子が悪い(消化不良)ことも体重が減る原因になります。
正常値でいるために
BMIを健康的な範囲に保つには、バランスの良い食事、適度な運動、そして規則正しい生活が大切です。無理のない方法で日々の習慣を整えましょう。
バランスの良い食事
食事では、主食(ご飯やパンなど)、主菜(肉や魚など)、副菜(野菜やサラダなど)をバランスよく食べることが大切です。
- 野菜を多めに:野菜中心の食事は低カロリーで満腹感が得られやすいので、肥満防止に効果的です。
- 高カロリーな食品を控える:スナック菓子や加工食品は控えめにしましょう。
- ゆっくり食べる:食事中によく噛むことで満腹感が得られ、食べすぎを防げます。
適度な運動
運動を日常生活に取り入れると、カロリーを消費して脂肪がたまりにくくなります。
- 有酸素運動:ウォーキングやランニングなどを1日30~60分行うと効果的です。
- 筋力トレーニング:週に2~3回、腕立て伏せやスクワットなどの筋トレを取り入れることで、筋肉量が増えて基礎代謝が上がります。
自分の体力に合わせて、無理のない範囲で始めましょう。
規則正しい生活
食事時間や睡眠時間を規則正しく保つことで、過食や栄養不足を防ぐことができます。
夕食は早めに済ませ、夜9時以降の食事は控えるのが理想です。
BMIの正常範囲を維持することは、健康的な身体づくりの基本です。
食事や運動習慣を見直し、無理なく継続できる方法で健康的な体重を目指しましょう。