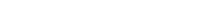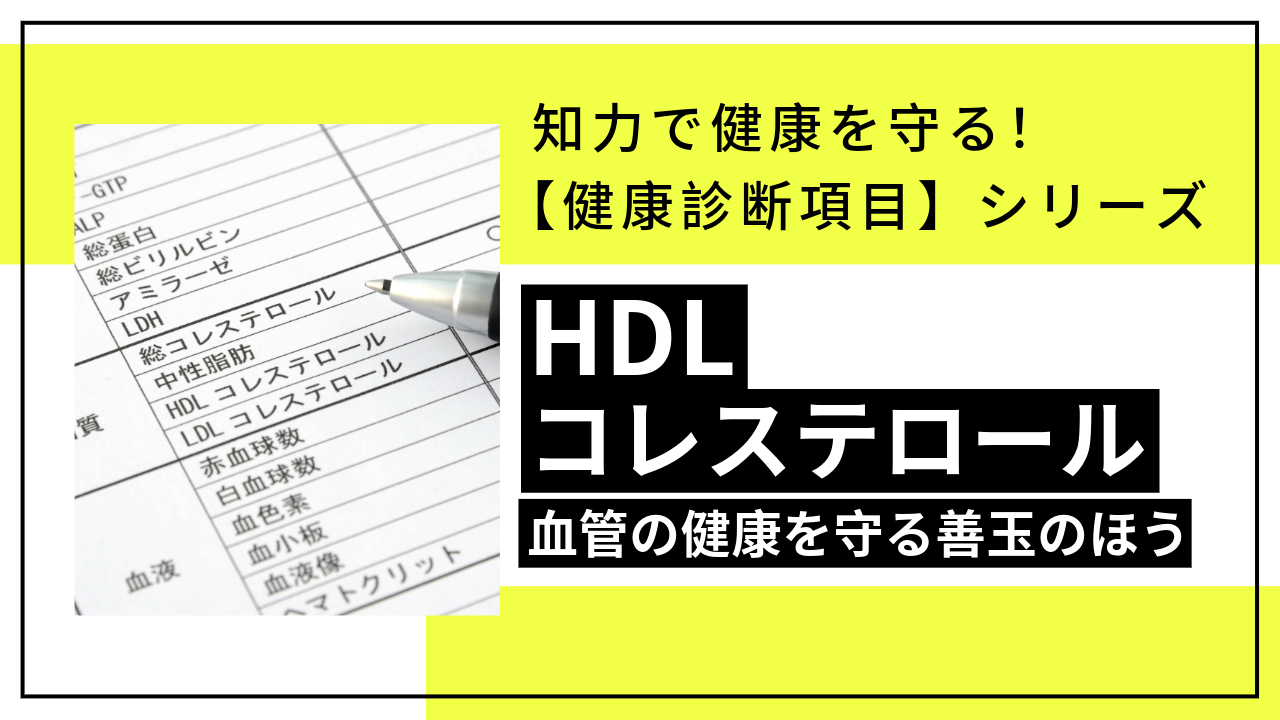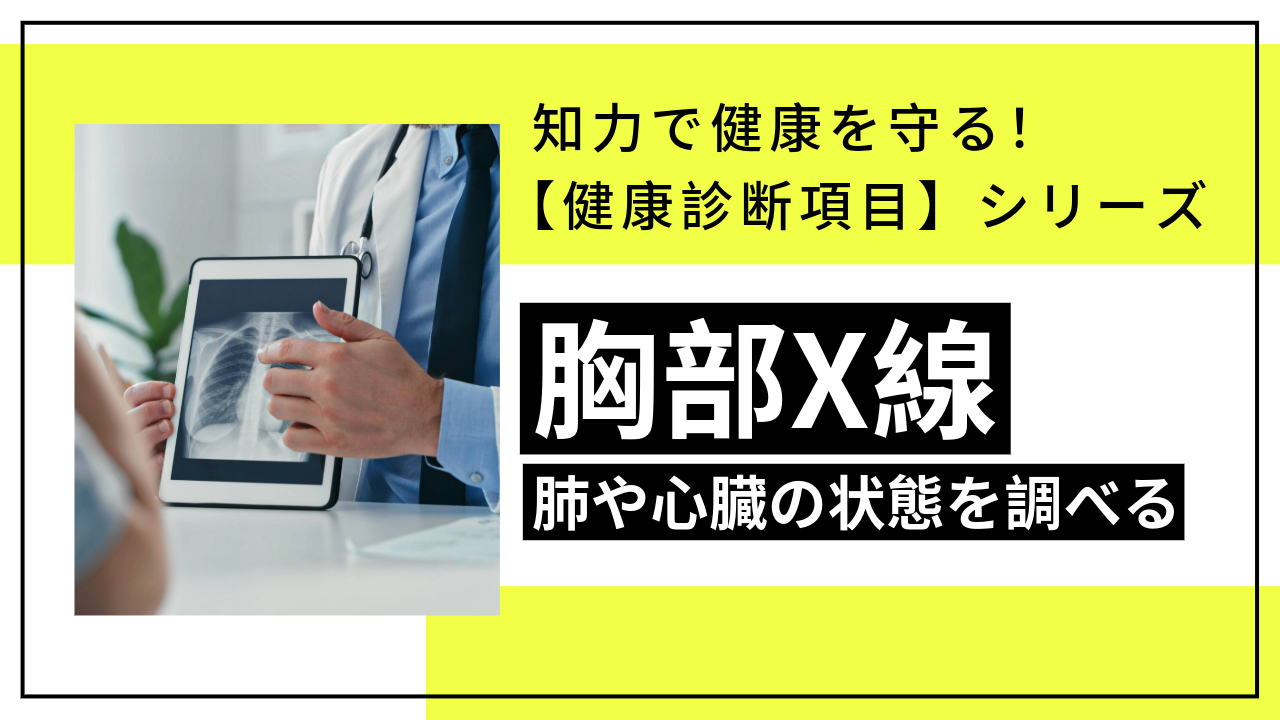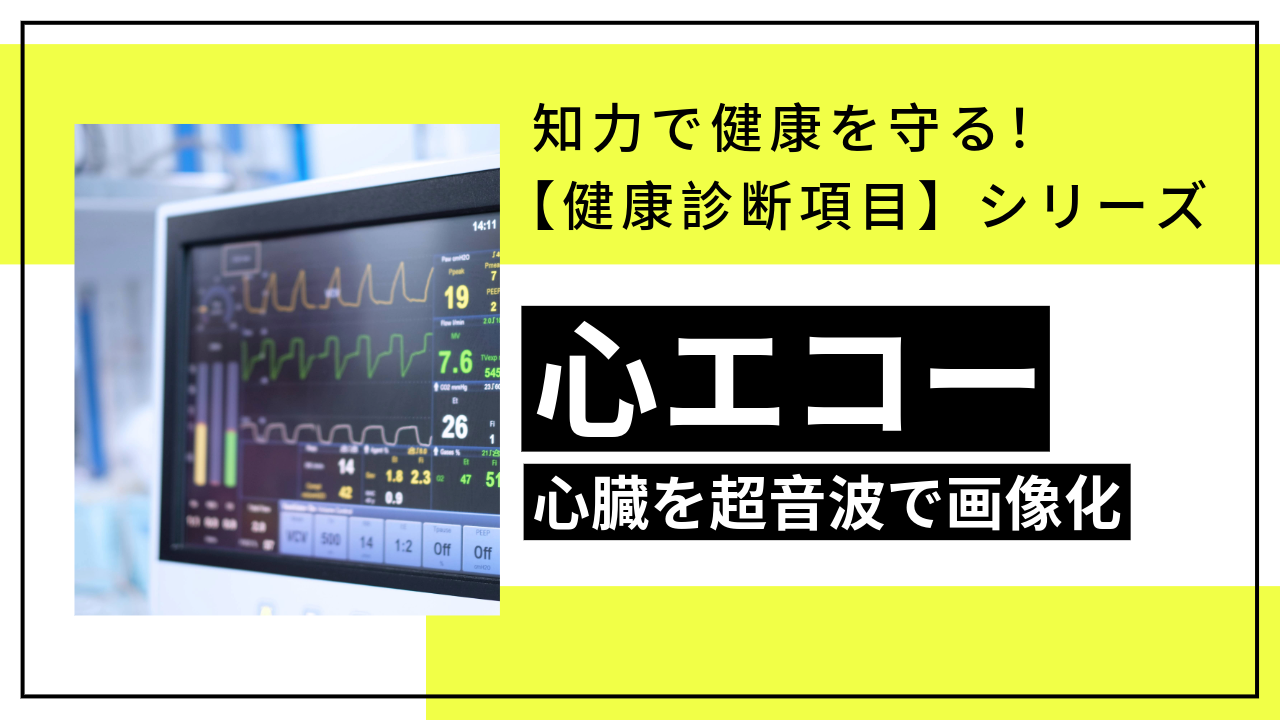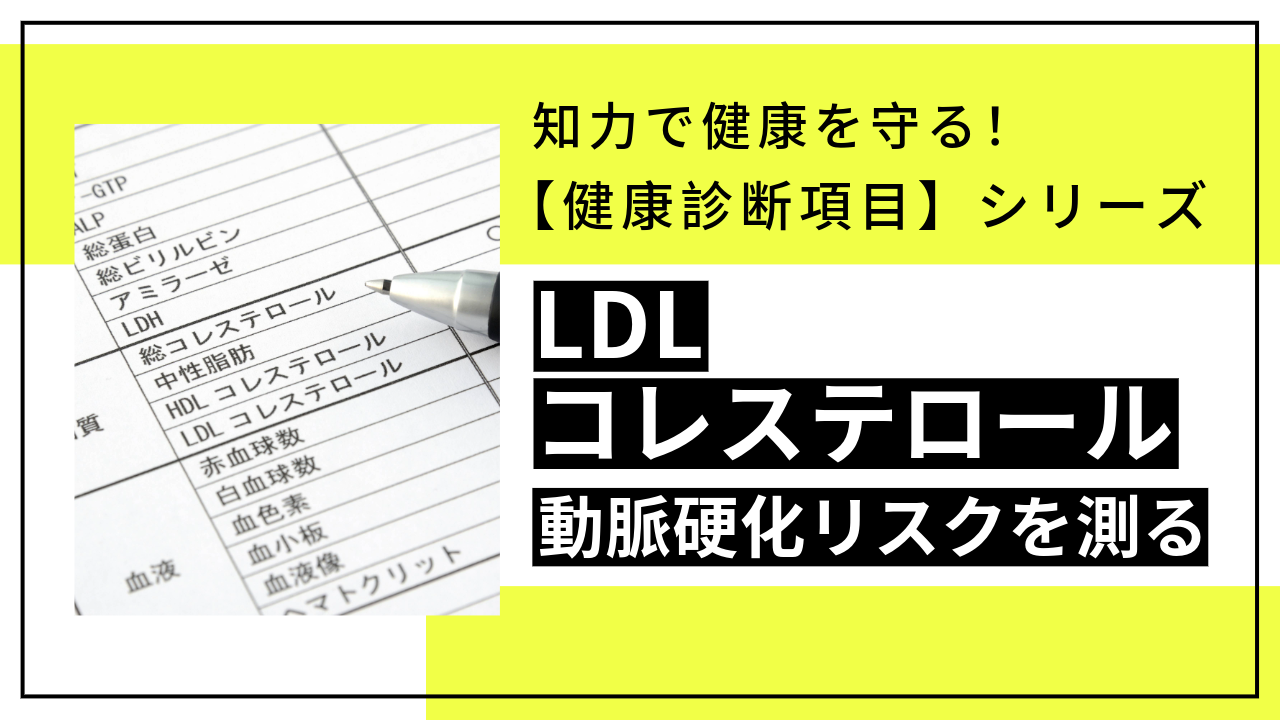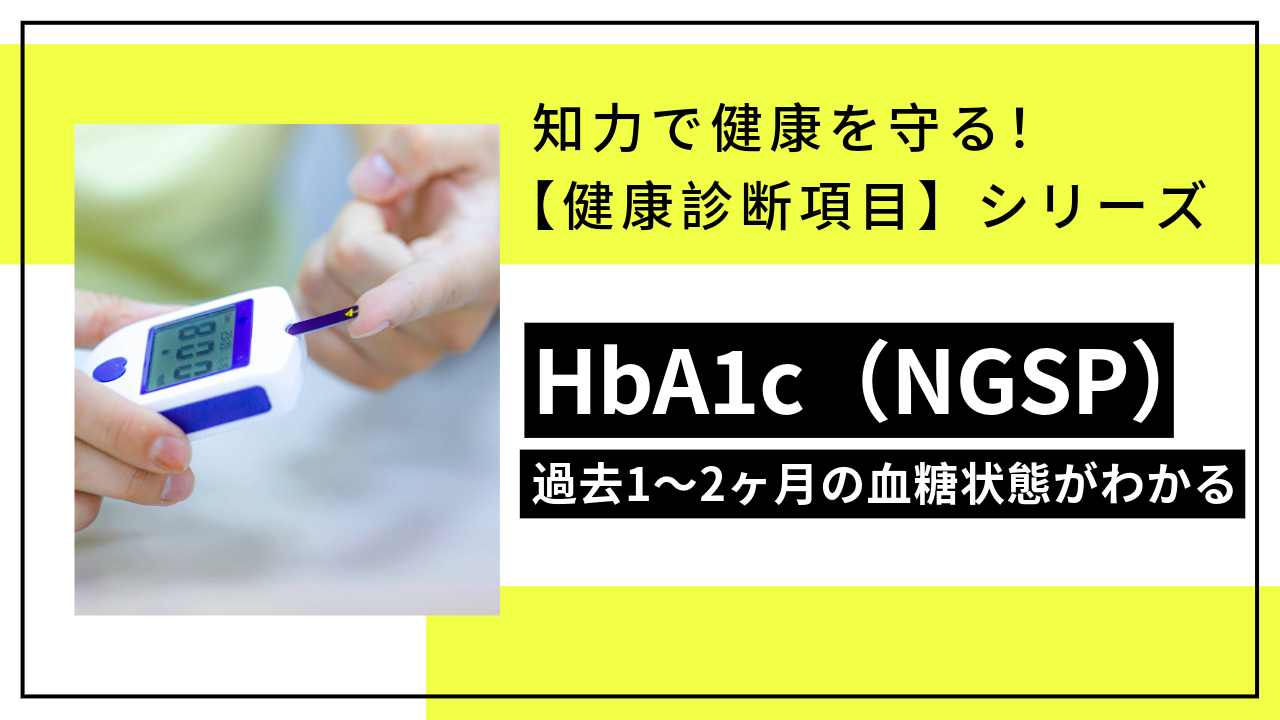【健康診断項目】「血圧」は塩分の摂りすぎに注意
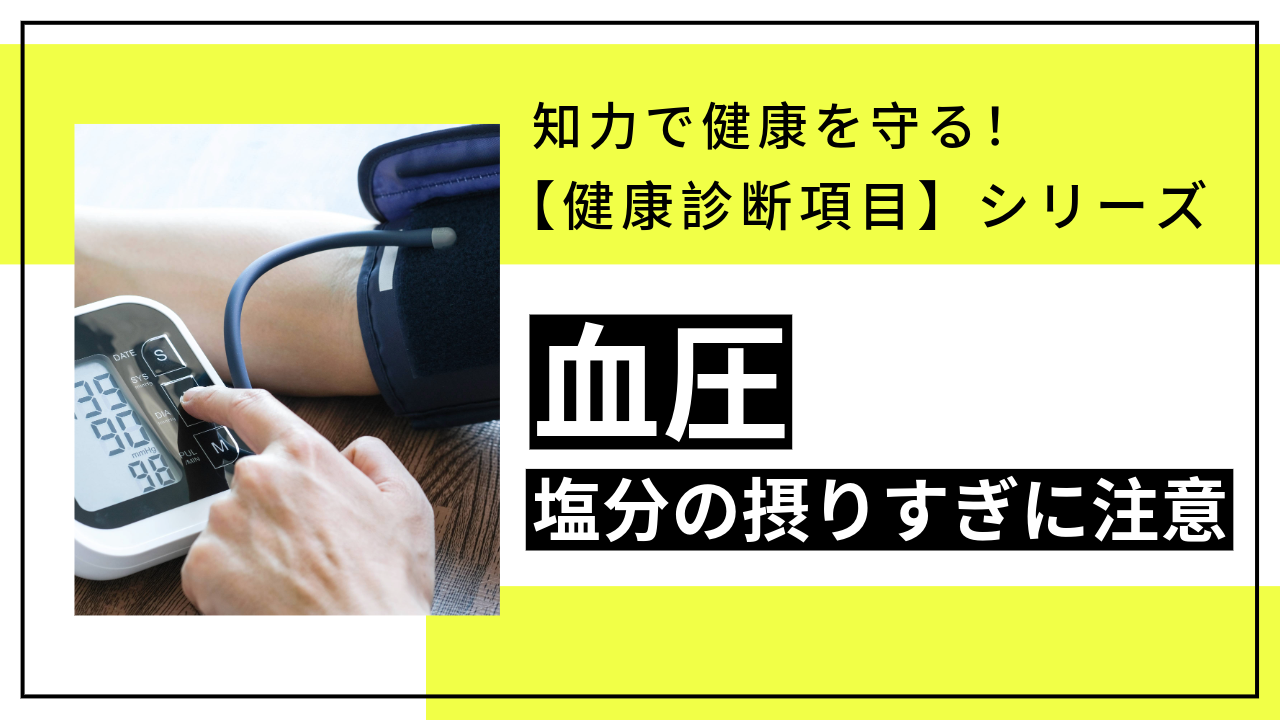
血圧とは?
血圧とは、心臓から出る血液が血管の壁を押す圧のことです。血圧は常に変動しており、日内変動があるほか、腎臓や神経などの内臓機能やホルモンバランスなどによっても変化します。
心臓は、全身に血液を循環するためにポンプのような動きをして収縮と拡張を繰り返しています。そのため、血圧は心臓の収縮と拡張によって高くなったり低くなったりします。心臓の収縮によって血液が血管にかける力が最大に達した時の血圧を「収縮期血圧」、収縮した心臓が拡張し、血管にかかる圧が最も低くなったときの値を「拡張期血圧」といいます。収縮期血圧は「上(の血圧)」、拡張期血圧は「下(の血圧)」と呼ばれることもあります。
正常値と異常値
血圧の正常値は、収縮期血圧が>=130mmHg、拡張期血圧が>=85mmHg以下1です。
この値を上回ると異常値となり「高血圧」と診断されます。
異常値だとどうなる?
血圧が高値になっても、ほとんどの場合自覚症状はありません。しかし、高血圧の状態が持続することで、本来柔らかく弾力性の高い血管が常に張り詰められた状態になります。すると、次第に血管が硬く厚くなる「動脈硬化」を生じます。動脈硬化は全身の至る血管に生じることがあり、心臓に栄養を供給する血管が詰まって心筋が壊死する「心筋梗塞」や、脳の血管が詰まる「脳梗塞」、ものを見る上で重要な役割がある「網膜」で出血する「眼底出血」などを来すことがあります。いずれも重篤な後遺症を残したり命に関わったりすることがあります。
異常値の原因は?
血圧が高くなる最大の原因は食塩の過剰摂取です。このほか、喫煙や飲酒、肥満、運動不足なども原因になります。
高血圧は原因によって大きく「二次性高血圧」と「本態性高血圧」に分けられます。二次性高血圧はホルモン異常などの病気が原因で高血圧になるものを指します。一方、本態性高血圧は食事や運動、喫煙、飲酒習慣などが原因となる「生活習慣病」で、日本人の高血圧のほとんどがこれにあたります。本態性高血圧でも日本人に多くみられる原因は食塩の摂り過ぎであるといわれています。
正常値でいるために
血圧を正常範囲に保つためには、生活習慣を整える必要があります。中でも、特に塩分の過剰摂取を控えることが重要です。「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、高血圧予防のため食塩摂取量を1日あたり6g未満とするよう記しています。2食塩の摂取量を減らすためには、外食や加工食品の摂取を控えるほか、調味料の使い過ぎに注意したり、低ナトリウム調味料を使用したりすることが有効です。
また、喫煙している場合には禁煙するようにし、節度ある適量の飲酒を心がけることも重要です。飲酒量は男性の場合には1日あたりビール中瓶1本程度とし、女性はその半量くらいを目安にしましょう。3
また、便秘を予防することも効果的です。便が出しにくくいきむ時間が長いと血圧が上がることがあります。便通をコントロールするため、毎日決まった時間に便座に座って排便の習慣をつけたり、食物繊維を多く含む食品を取り入れたりすると良いでしょう。
このほか、肥満である場合には適正体重を目指して減量し、十分な睡眠や適度な運動を心がけましょう。
参考文献
・一般社団法人日本循環器病予防学会「血圧測定」
・国立研究開発法人国立循環器病研究センター「高血圧」
・特定非営利活動法人日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」
・特定非営利活動法人日本高血圧学会 一般向け「高血圧治療ガイドライン2019」解説冊子「高血圧の話」
・公益社団法人日本眼科学会「網膜静脈分枝閉塞症」
・厚生労働省e-ヘルスネット「脳卒中」
・厚生労働省e-ヘルスネット「狭心症・心筋梗塞などの心臓病(虚血性心疾患)」