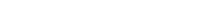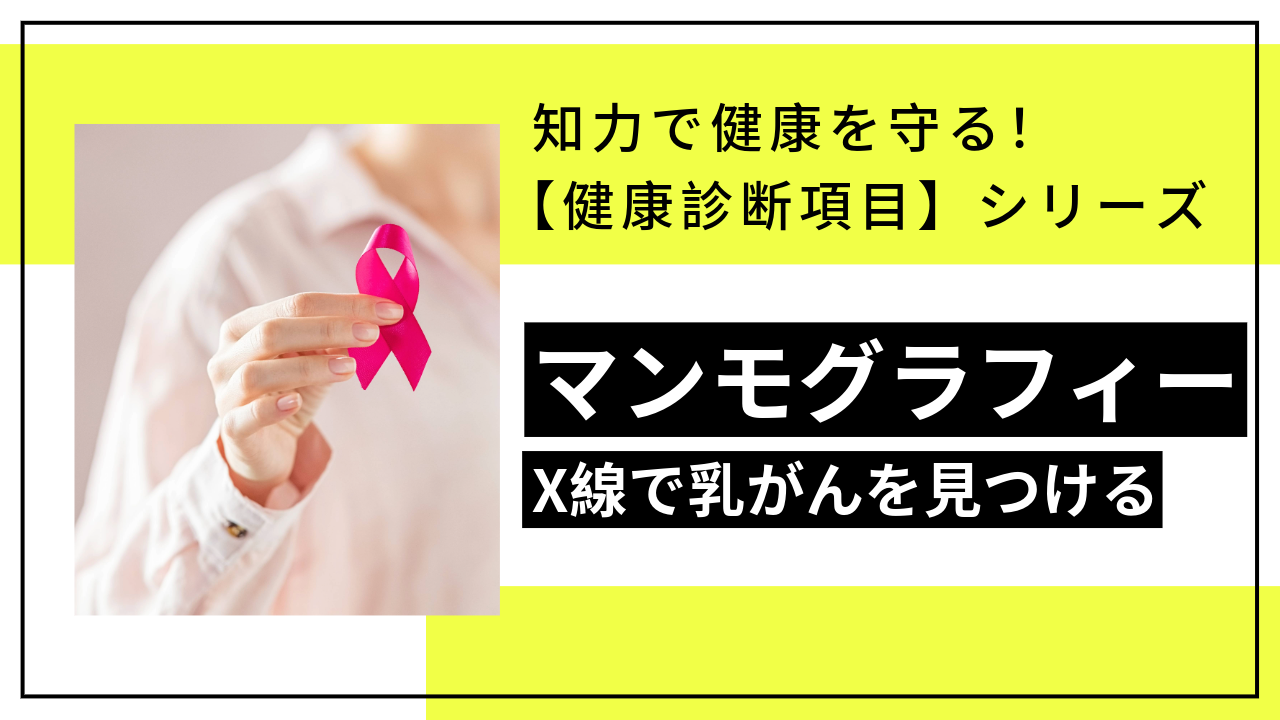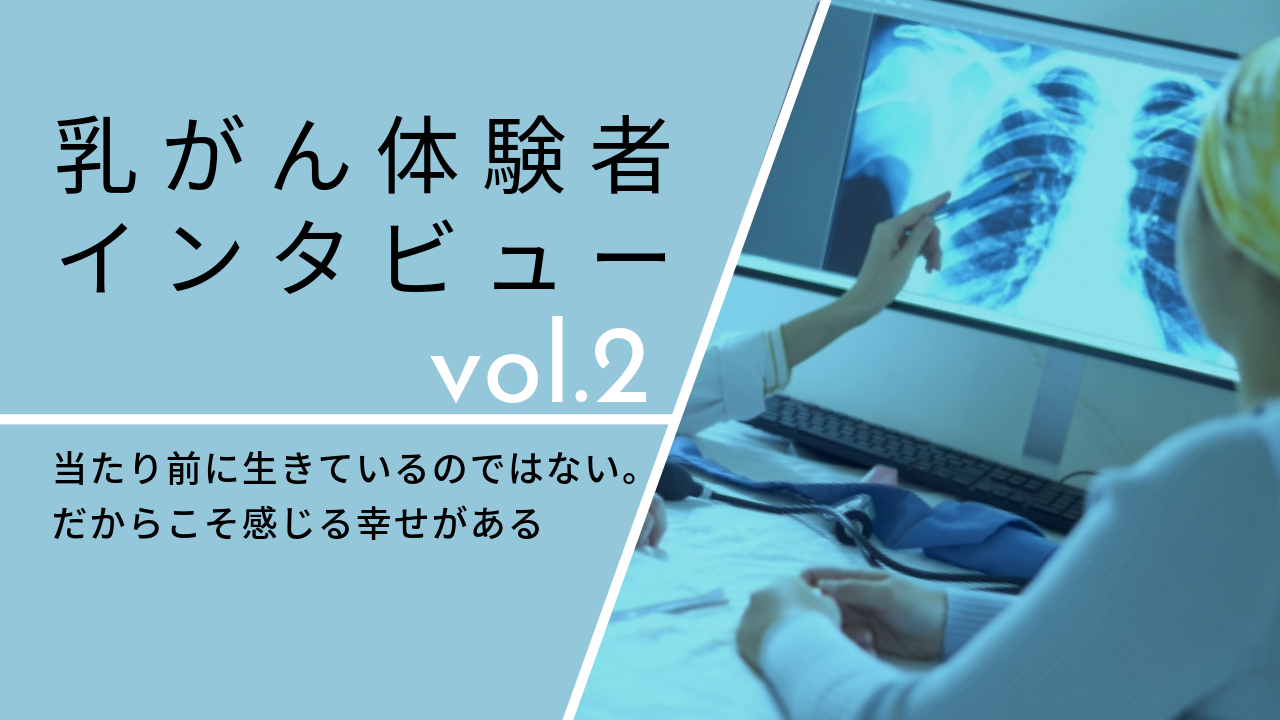【乳がん】要注意健康診断項目とその他の検査法

乳がんに関連する健康診断項目
乳がんの発症リスクを調べるための健康診断項目として重要なのは「BMI」と「乳がん検診」です。これらの項目は、乳がんの早期発見や予防に役立ちます。
乳がん検診では、以下のような検査が行われます。
問診では、乳がんリスクの有無を確認します。
- 家族に乳がんの人がいるか(親族が発症した年齢や治療歴など)
- 初潮(最初の生理)の年齢
- 閉経の年齢
- 妊娠や出産の経験
これらの情報は、乳がんの発症リスクを評価するために重要です。
マンモグラフィーは、乳がん検診で最も広く用いられる検査で、特に40歳以上の女性を対象としています。この検査では、乳房を軽く押してX線で撮影し、乳腺やしこり、石灰化の有無を確認します。
- 40~49歳の女性:「内外斜位方向」と「頭尾側方向」の2方向から撮影し、詳細に乳房を検査します。
- 50歳以上の女性:「内外斜位方向」の1方向のみの撮影が一般的です。1
生理前や生理中は乳房が張って痛みを感じやすいため、生理が終わった数日後に検査を受けるのが望ましいとされています。
乳がん検診に加えて、定期的なセルフチェックも大切です。
- 乳房にしこりや痛みがないか
- 乳頭から分泌物が出ていないか
- 皮膚にくぼみや引きつれがないか
異変に気付くために、上記のポイントを習慣的に確認しましょう。
各健康診断項目の正常値と異常値
BMIの正常値と異常値は以下の通りです。
| 分類 | BMI |
|---|---|
| 低体重 | 18.5未満 |
| 標準体重 | 18.5〜24.9 |
| 肥満1 | 25.0以上30.0未満 |
| 肥満2 | 30.0以上35.0未満 |
| 肥満3 | 35.0以上40.0未満 |
| 高度肥満 | 40.0以上 |
参照:一般社団法人日本肥満学会「肥満症診療ガイドライン2022」
マンモグラフィーの判断基準は以下の通りです。2
| カテゴリー | 判定 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 異常なし |
| カテゴリー2 | 良性 |
| カテゴリー3 | 良性かもしれないが、悪性の可能性もある |
| カテゴリー4 | 悪性の可能性あり |
| カテゴリー5 | 悪性の可能性が非常に高い |
乳腺にしこりや異常な石灰化が見つかることがあります。
もし悪性腫瘍(がん)の疑いがある場合、しこりの形がはっきりしなかったり、石灰化の形が不規則だったりすることが特徴です。
このような場合は、さらに詳しい検査を行う必要があります。
その他の検査
乳がんでは、マンモグラフィー以外に以下のような検査が行われることがあります。
- 超音波検査
- 細胞診(病理検査)
- 組織診(病理検査)
この検査でわかること
超音波検査
超音波検査では、乳房の中にしこりがあるかどうか、その大きさ、さらにわきの下のリンパ節にがんが広がっているかを調べます。
この検査は、乳腺が密集している若い女性や妊娠中の女性、また乳腺密度が高いデンスブレストの人に適している場合があります。
超音波検査は乳房にジェルを塗り、プローブと呼ばれるセンサーを当てることで乳房内部を観察するため、痛みが少ないのが特徴です。
また、良性か悪性かを判断する際、しこりの形や輪郭、硬さ、血流の有無が手がかりとなります。
ただし、超音波検査では乳がんの一部に見られる「石灰化」を判断するのは難しいため、超音波検査とマンモグラフィーを併用することもあります。
細胞診(病理検査)
乳がんの細胞診は、しこりや乳頭の異常など病変が見つかった際に、がん細胞かどうかを判断するための検査です。
穿刺吸引細胞診では、細い針をしこりに刺し、吸引した細胞を調べます。比較的痛みが少なく、麻酔を伴わないため身体への負担が少ないです。
細胞診の診断結果は、以下の5つのクラスに分かれます。
- クラスI:正常な細胞
- クラスII:ほぼ正常な細胞
- クラスIII:判断がつかない(良性と悪性の境界的)
- クラスIV:がんの疑いが高い細胞
- クラスV:がん細胞の可能性が非常に高い
細胞診では、がんかどうか確定できないこともあります。
クラスIII以上の場合、結果だけで判断するのは難しいため、他の検査(組織診など)を併用して詳しく調べることが一般的です。
組織診(病理検査)
組織診は、乳房の病変がある部分から組織の一部を取り出して調べる検査です。
細胞だけを調べる細胞診と異なり、組織全体を採取するため、より正確に病変の性質を診断できます。
組織診には、以下の2つの方法があります。
- 針生検
局所麻酔をして太めの針を使い、病変から組織を採取する方法です。
「マンモトーム生検」と呼ばれる吸引式の方法では、多くの組織を採取でき、詳しい検査が可能です。
- 外科的生検
必要に応じて皮膚を少し切り、しこり全体やその一部を取り出す方法です。
より詳しい病理検査を行うために使われます。
組織診は、診断精度が高く、正確に良性と悪性の判定ができることが利点です。
ただし、細胞診よりも多くの組織を採取するため、体への負担が大きくなることがあります。検査後は出血のリスクがあるため、当日は飲酒や激しい運動・入浴を控える必要があります。
この検査はどこで受ける?
乳腺外科やがん専門の医療機関で受けることができます。
健診施設や主治医から紹介状をもらい、専門医の診察を受けるのが一般的です。
乳がんになりやすい体質や遺伝のリスクがある人は、早めに乳がん検診を始めることが大切です。
家族に乳がんや卵巣がんの人がいる場合は、遺伝に関する検査を行うことで、自分ががんになりやすい体質かを知ることができ、予防や検診の計画を早めに立てることができます。
乳がんを早く見つけることで、治療の選択肢が増え、治療後の経過(予後)も良くなる可能性が高まります。自分の体質や家族の病歴を把握し、早めに検診を受けることをおすすめします。